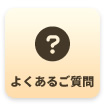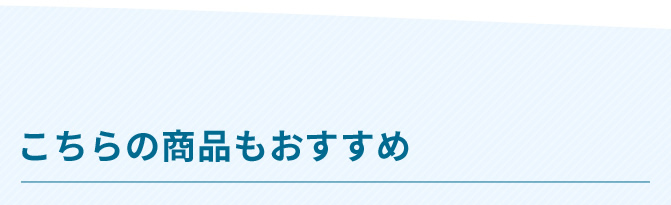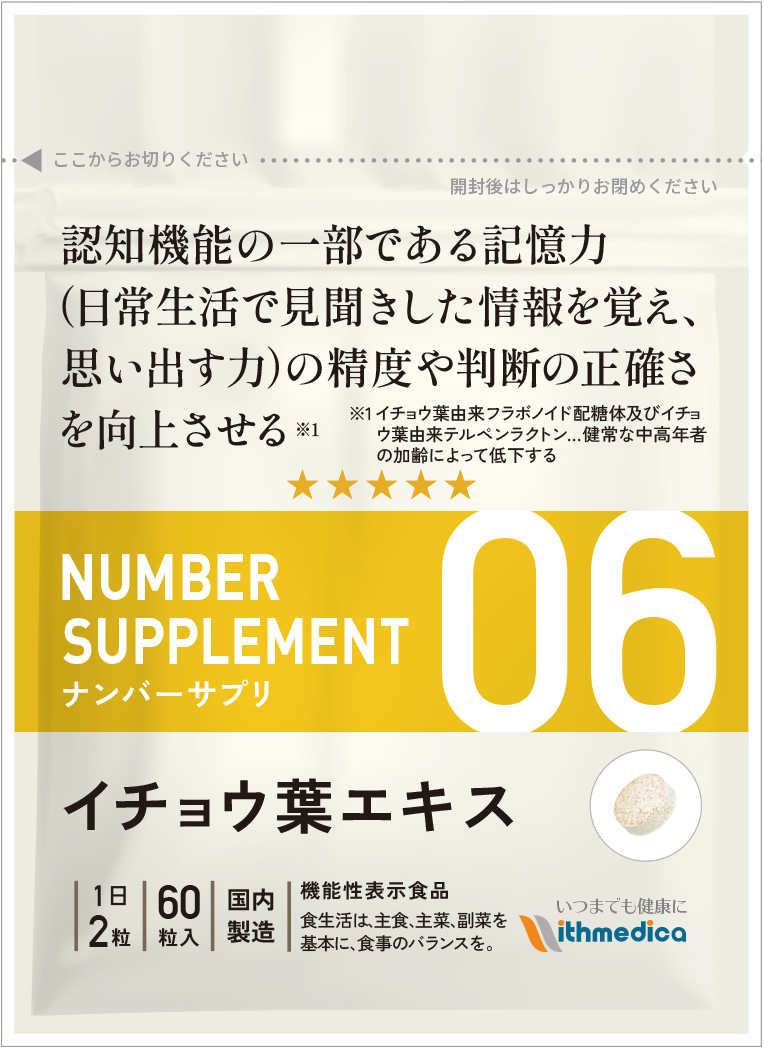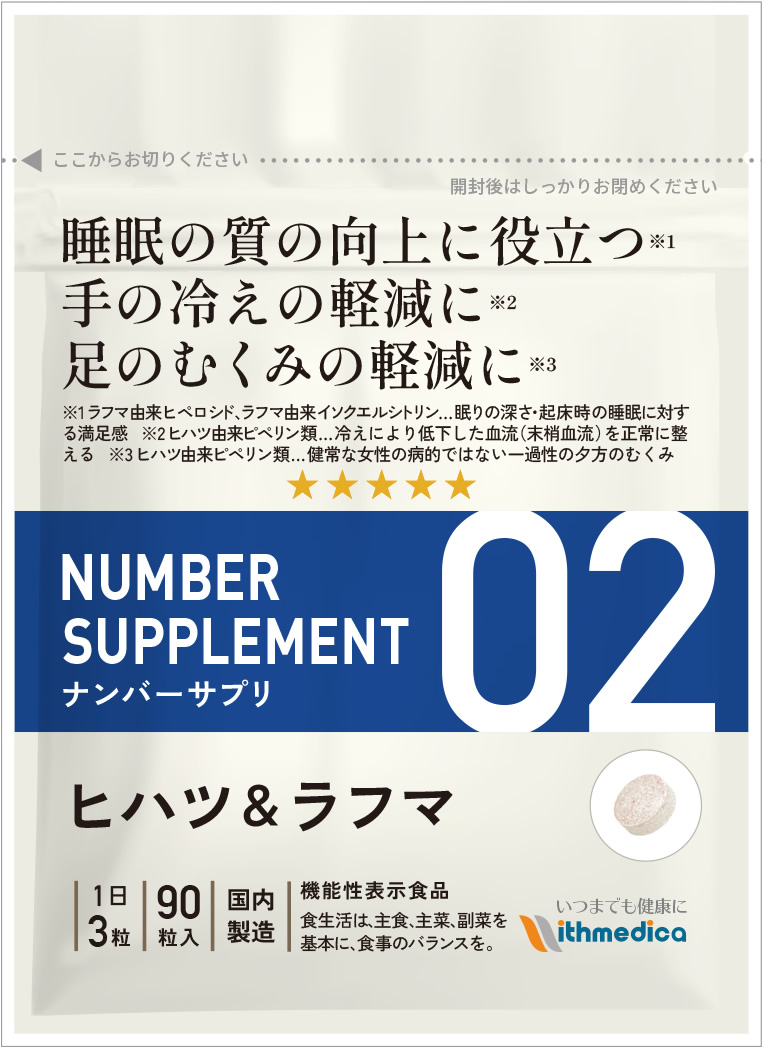生活習慣を見直そう!逆流性食道炎治療の基本。について
執筆者: 永田健(消化器内科医)
[記事公開日] 2023-03-19 [最終更新日] 2024-07-03
[ 目次 ]

逆流性食道炎ってなに?
逆流性食道炎とは、胃酸など胃内容物が食道に逆流し長い時間とどまることで、食道粘膜が刺激され、炎症が生じ傷ついた状態をいいます。
人口の10%~20%にみられる頻度の高い疾患で、特に中高年・高齢者に多く、ヘリコバクターピロリ感染率の低下や、食生活の欧米化とともに、今後も増加することが予想されています。
命に別条はないため、軽く見られがちなこの病気ですが、食後だけでなく昼夜を問わず不快な症状が続くため、日常生活の質をいちじるしく低下させてしまいます。さらに長期的には食道腺癌のリスクもあがるため侮ってはいけない病気なのです!
人口の10%~20%にみられる頻度の高い疾患で、特に中高年・高齢者に多く、ヘリコバクターピロリ感染率の低下や、食生活の欧米化とともに、今後も増加することが予想されています。
命に別条はないため、軽く見られがちなこの病気ですが、食後だけでなく昼夜を問わず不快な症状が続くため、日常生活の質をいちじるしく低下させてしまいます。さらに長期的には食道腺癌のリスクもあがるため侮ってはいけない病気なのです!
逆流性食道炎の原因は生活習慣にあり!
食道と胃のつなぎ目には下部食道括約筋という筋肉が存在し、健康な人ではこの筋肉がしっかりと収縮しているため、簡単には胃内容物の逆流は起きません。しかし年齢を重ねることでの筋力低下や、肥満(特に内臓脂肪量の増加)、食べた後すぐに横になるなどの悪い姿勢で生じる胃の内圧上昇によって下部食道括約筋が緩み、胃内容物の逆流が起きてしまいます。
また近年では、食の欧米化によって高脂肪食を食べる機会が増加しています。消化に時間のかかる高脂肪食は、胃に長い時間とどまるため胃酸が過剰に分泌されてしまい、逆流症状を悪化させると報告されています。
これらの悪い生活習慣に思い当たる方も多いのではないでしょうか?
また近年では、食の欧米化によって高脂肪食を食べる機会が増加しています。消化に時間のかかる高脂肪食は、胃に長い時間とどまるため胃酸が過剰に分泌されてしまい、逆流症状を悪化させると報告されています。
これらの悪い生活習慣に思い当たる方も多いのではないでしょうか?
「胸やけ」だけじゃない!逆流性食道炎の症状はさまざまです。
逆流性食道炎の主な症状は「胸やけ」と「呑酸」で、食道内への胃酸逆流によって生じます。ただしひとくちに「胸やけ」といっても、患者さんによって「ムカムカする」「酸っぱいものがあがってくる」「胃がおもたい」など症状はさまざまです。
また食道以外の症状として、「長期間つづく咳」や「喘息」などの呼吸器症状や、「のどの痛み」などの耳鼻咽喉科症状、非心臓性の「胸のいたみ」などがあります。これは胃酸が食道を越えてどの程度までこみ上げてくるかによって症状が変わるからです。
一見すると食道と関係なさそうなこれらの症状をきっかけに、逆流性食道炎の診断にいたる場合も多々あります。気になる症状がある場合は、我慢せず病院を受診し医師に相談しましょう!
また食道以外の症状として、「長期間つづく咳」や「喘息」などの呼吸器症状や、「のどの痛み」などの耳鼻咽喉科症状、非心臓性の「胸のいたみ」などがあります。これは胃酸が食道を越えてどの程度までこみ上げてくるかによって症状が変わるからです。
一見すると食道と関係なさそうなこれらの症状をきっかけに、逆流性食道炎の診断にいたる場合も多々あります。気になる症状がある場合は、我慢せず病院を受診し医師に相談しましょう!
逆流性食道炎の診断には、胃カメラを受けましょう!
病院ではまず問診が行われます。「胸やけ」などの症状から逆流性食道炎が疑われた場合は、内視鏡検査(胃カメラ)で診断します。胃カメラは、病院や人間ドック、健診施設で受けられます。口から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸の一部までの消化管粘膜を詳細に観察し、所要時間は7分から10分程度です。
内視鏡検査では、食道と胃のつなぎ目である食道胃接合部(EGJ:Esophago-Gastric Junction)における食道粘膜障害の有無を確認します。さらに粘膜障害の拡がりの程度によって、6段階の重症度に分類されます。食道粘膜障害の程度と症状は相関しない場合も多々ありますが、それぞれの重症度に応じて治療方針を検討します。
しんどくてツライ検査の代名詞ともいえる胃カメラですが、最近では鼻から挿入する細い内視鏡や、静脈麻酔下で内視鏡を挿入する方法が普及しており、苦痛を少なく検査が受けられるようになっています。ツラいのは一瞬です、頑張って乗り切りましょう!
内視鏡検査では、食道と胃のつなぎ目である食道胃接合部(EGJ:Esophago-Gastric Junction)における食道粘膜障害の有無を確認します。さらに粘膜障害の拡がりの程度によって、6段階の重症度に分類されます。食道粘膜障害の程度と症状は相関しない場合も多々ありますが、それぞれの重症度に応じて治療方針を検討します。
しんどくてツライ検査の代名詞ともいえる胃カメラですが、最近では鼻から挿入する細い内視鏡や、静脈麻酔下で内視鏡を挿入する方法が普及しており、苦痛を少なく検査が受けられるようになっています。ツラいのは一瞬です、頑張って乗り切りましょう!

生活習慣の改善は、逆流性食道炎の治療の基本です!
逆流性食道炎は生活習慣病のひとつと考えられており、生活習慣を改めることで症状改善が期待できます!
関連する生活習慣として、BMI(body mass index)、腹囲、内臓脂肪量、コレステロール値、喫煙習慣などが報告されています。バランスのよい食生活、適度な運動などの規則正しい生活習慣は全ての基本です。さらにはそのほかの生活習慣病(肥満・高血圧・高脂血症など)の予防にもつながるため、生活習慣の改善で一石二鳥・三鳥を目指しましょう。
具体的な改善方法として、まずは食習慣の改善です。食べ過ぎや早食いはできるだけ避けてください。また就寝直前に食事をすると消化が不十分となり、寝ている間に胃酸が過剰に分泌されてしまいます。食後2~3時間は横にならないように心がけ、食後の軽いウォーキング運動なども消化を促進するのでおすすめです。
食事内容については、アルコールや高脂肪食は控えめにして、野菜・果物・全粒穀物・魚類・ナッツなどを中心としたものに変えてみましょう。これらの食事は、逆流症状を抑えるといわれています。
加えて、肥満の方はダイエットして体重を減らす努力が必要です。内臓脂肪を減らすことで腹圧および胃内圧を下降でき、逆流症状改善が期待できます。
また禁煙も逆流性食道炎治療の一つとして重要です。喫煙者には逆流症状の頻度が高いと報告されており、これは喫煙が唾液による胃酸中和能力を低下させるためと考えられています。最近の研究では禁煙成功者の43%で逆流症状改善効果がみられたと報告されており、禁煙も有効な治療法といえるでしょう。
関連する生活習慣として、BMI(body mass index)、腹囲、内臓脂肪量、コレステロール値、喫煙習慣などが報告されています。バランスのよい食生活、適度な運動などの規則正しい生活習慣は全ての基本です。さらにはそのほかの生活習慣病(肥満・高血圧・高脂血症など)の予防にもつながるため、生活習慣の改善で一石二鳥・三鳥を目指しましょう。
具体的な改善方法として、まずは食習慣の改善です。食べ過ぎや早食いはできるだけ避けてください。また就寝直前に食事をすると消化が不十分となり、寝ている間に胃酸が過剰に分泌されてしまいます。食後2~3時間は横にならないように心がけ、食後の軽いウォーキング運動なども消化を促進するのでおすすめです。
食事内容については、アルコールや高脂肪食は控えめにして、野菜・果物・全粒穀物・魚類・ナッツなどを中心としたものに変えてみましょう。これらの食事は、逆流症状を抑えるといわれています。
加えて、肥満の方はダイエットして体重を減らす努力が必要です。内臓脂肪を減らすことで腹圧および胃内圧を下降でき、逆流症状改善が期待できます。
また禁煙も逆流性食道炎治療の一つとして重要です。喫煙者には逆流症状の頻度が高いと報告されており、これは喫煙が唾液による胃酸中和能力を低下させるためと考えられています。最近の研究では禁煙成功者の43%で逆流症状改善効果がみられたと報告されており、禁煙も有効な治療法といえるでしょう。
生活習慣を見直しても良くならないときは、お薬の内服が必要です。
内服治療には、主にプロトンポンプ阻害剤(PPI)というお薬が用いられています。一般的には8週間PPIを投与され、この8週間の治療で粘膜障害が改善しなかったり、症状が消失しなかったりする場合は難治症例として扱います。難治症例に対しては、PPIの増量や分割投与、他の胃酸分泌抑制薬や胃運動改善薬を投与し、一日を通して胃酸分泌を抑制することを目指します。
近年、新しい胃酸分泌抑制薬としてカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)が登場しました。従来のPPIと比較してとても強力な胃酸分泌抑制作用を有しており、難治症例に対しても高い治療効果が報告されています。
近年、新しい胃酸分泌抑制薬としてカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)が登場しました。従来のPPIと比較してとても強力な胃酸分泌抑制作用を有しており、難治症例に対しても高い治療効果が報告されています。
まとめ
逆流性食道炎は直接命にかかわる病気ではありませんが、症状が強い場合は生活の質をいちじるしく低下させてしまいます。生活習慣を見直しても症状が続くときは我慢せず病院を受診し医師に相談しましょう。