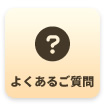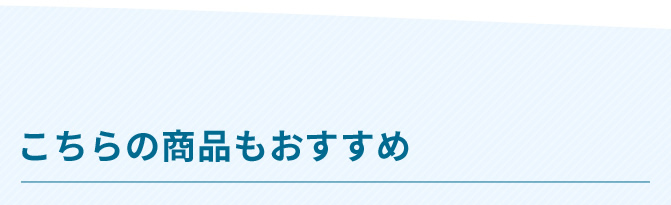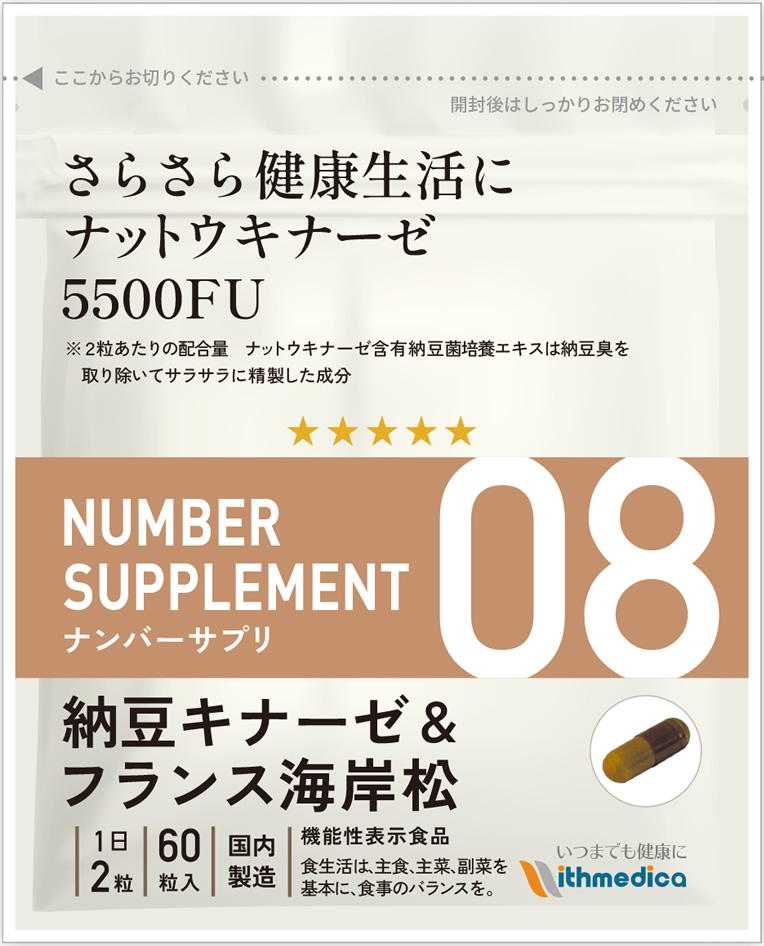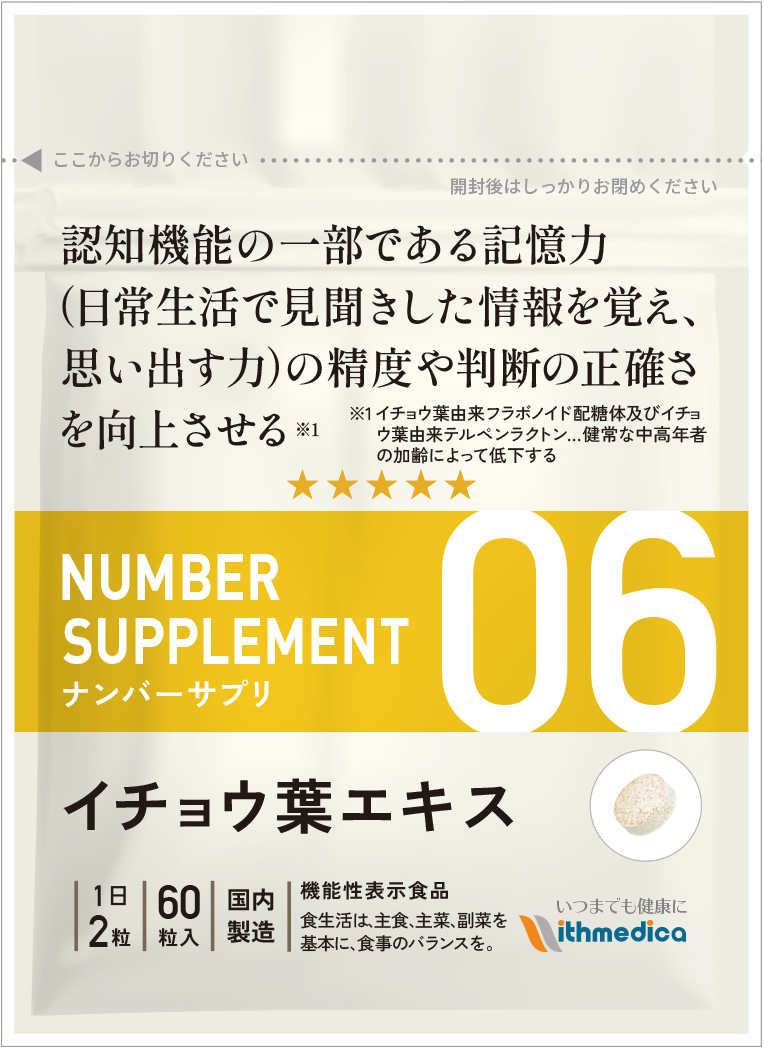管理栄養士が教える減塩の基礎と具体的な方法6選!について
執筆者: 中村友也(管理栄養士)
[記事公開日] 2023-05-09 [最終更新日] 2023-05-16
この記事では、減塩を行う際に知っておくべき基本情報と具体的な方法6選を紹介したいと思います!
[ 目次 ]

塩分とはどんなもの?
多くの食品に含まれている塩分(ナトリウム)は体の中でどのような働きをしているのでしょうか?
ナトリウムは人体に必要なミネラルの一種で、主に体内のミネラルや水分のバランスに関係しています。
人間が生きていく上でナトリウムは必要な栄養素ですが、肉や魚、野菜など食材そのものにも含まれており基本的に欠乏するものではありません。むしろ摂り過ぎが問題となっています。
ナトリウムは人体に必要なミネラルの一種で、主に体内のミネラルや水分のバランスに関係しています。
人間が生きていく上でナトリウムは必要な栄養素ですが、肉や魚、野菜など食材そのものにも含まれており基本的に欠乏するものではありません。むしろ摂り過ぎが問題となっています。
塩分摂取量の平均値と目標値とは?
日本人の1日の平均塩分摂取量は男性約11g、女性約9gとなっています。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では高血圧等の疾患がない場合でも、1日の塩分摂取量の目標値は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。
そのため、現代の日本人は塩分の摂りすぎであると言われています。
また、高血圧や慢性腎臓病の重症化予防のためには、1日の塩分摂取量を6g未満にすることを目標としているため、かなり意識しないと減塩は難しいということがわかります。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では高血圧等の疾患がない場合でも、1日の塩分摂取量の目標値は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。
そのため、現代の日本人は塩分の摂りすぎであると言われています。
また、高血圧や慢性腎臓病の重症化予防のためには、1日の塩分摂取量を6g未満にすることを目標としているため、かなり意識しないと減塩は難しいということがわかります。
日本人は世界的にみても塩分摂取量が多い
日本は、和食に用いられる醤油や味噌の塩分含有量が多いため、世界的にみても塩分摂取量が多い国です。そのため、我々日本人は普段から塩分摂取量を意識していないと過剰摂取につながりやすい環境にいると言えます。
塩分を多く含む食品の例
調味料などの他にも、ハムやウインナー、ちくわやはんぺんなどの加工品にも塩分が含まれているため注意が必要です。
これらの食品は発色や成形のためにナトリウムを利用しており、食品そのものに多くの塩分が含まれているため、追加で味付けをすることでより塩分量が増えてしまいます。
これらの食品は発色や成形のためにナトリウムを利用しており、食品そのものに多くの塩分が含まれているため、追加で味付けをすることでより塩分量が増えてしまいます。
減塩の方法6選!
塩味以外の味を活用する
減塩をする際は、塩味以外の酸味や辛味などを活用しましょう。
減塩をすると料理の味が薄くなり、美味しく感じないという方も多いです。
しかし、料理の味は塩味だけではなく酸味や苦味、甘味など様々な味の重なりによって決まるため、塩味以外を活用することで減塩を達成しましょう。
例えば、お酢やレモン、一味や砂糖など塩分を含まない調味料、食材を活用して料理をするのがおすすめです。
H3比較的塩分の少ない調味料を使う
比較的&塩分含有量が少ない調味料の活用も視野に入れましょう。
例えば、ポン酢やマヨネーズ、ケチャップなどは味がしっかりしていますが比較的塩分が少ない調味料と言えます。使いすぎはよくありませんが、塩や醤油などの塩分の多い調味料の代わりに使うことを検討してみてください。
H3減塩調味料を使う
醤油や味噌、塩コショウなどの調味料は、減塩調味料と呼ばれるものが販売されているため、それらを用いるのも効果的です。
塩分は、正確には塩化ナトリウムという物質で存在いることが多く、この物質を摂取することで塩味を感じることができます。
しかし、減塩調味料はこの塩化ナトリウムの代わりに同じく塩味を感じる塩化カリウムと呼ばれる物質を使用しています。
この塩化カリウムにはナトリウムが含まれていないため、減塩に役立てることができます。
普段減塩の調味料を使っていないという方は、こういったものに置き換えてみるのもおすすめです。
H3 直前に味付けする
料理をする際は、直前に味付けするようにしましょう。
味がしみこんでいるほうがおいしいからと下味をつけてから調理をする方も多いと思いますが、その場合調味料がしみこみすぎて塩分過多になる可能性が高いです。
そのため、味付けは直前に行い、食材の表面に味がつくようにしましょう。
H3風味を効かせる
だしやスパイスを使って風味を効かせるのも減塩に有効な方法です。
我々が料理を美味しいと感じる要素の中で、味覚以外に嗅覚も大きな役割を担っています。
そのため、だしを効かせたり、コショウやハーブなどのスパイス等を活用することで風味がよくなり、味の薄さが気にならない料理に仕上げることができます。
しかし、顆粒だしや塩コショウなどには塩分が含まれていますので、だしは鰹節や昆布から直接取る、スパイスやハーブは単体のものを活用するようにしましょう。
H3焼き色をつけるなどして香ばしさを
香りや食感をよくするために、焼き色を付けて料理に香ばしさを与えるのも減塩に有用です。
鶏や魚の皮をパリッと焼いてあげるだけでも料理に香ばしさがプラスされ、食欲が増進されます。
また、焼き色をつけるだけならば味の調整が必要ないため、料理が苦手な方でもチャレンジしやすい方法ですね。
H3見た目を整える
味覚、嗅覚以外に視覚も料理のおいしさの一端を担っていますので、料理の見た目を整えることを意識するのも減塩に効果的です。
きれいなお皿を使ったり、盛り付けにこだわることで料理がおいしそうにみえます。
減塩食の味に満足できないからこそ、味以外の要素に力を入れることで楽しく減塩食が継続できます。
減塩をする際は、塩味以外の酸味や辛味などを活用しましょう。
減塩をすると料理の味が薄くなり、美味しく感じないという方も多いです。
しかし、料理の味は塩味だけではなく酸味や苦味、甘味など様々な味の重なりによって決まるため、塩味以外を活用することで減塩を達成しましょう。
例えば、お酢やレモン、一味や砂糖など塩分を含まない調味料、食材を活用して料理をするのがおすすめです。
H3比較的塩分の少ない調味料を使う
比較的&塩分含有量が少ない調味料の活用も視野に入れましょう。
例えば、ポン酢やマヨネーズ、ケチャップなどは味がしっかりしていますが比較的塩分が少ない調味料と言えます。使いすぎはよくありませんが、塩や醤油などの塩分の多い調味料の代わりに使うことを検討してみてください。
H3減塩調味料を使う
醤油や味噌、塩コショウなどの調味料は、減塩調味料と呼ばれるものが販売されているため、それらを用いるのも効果的です。
塩分は、正確には塩化ナトリウムという物質で存在いることが多く、この物質を摂取することで塩味を感じることができます。
しかし、減塩調味料はこの塩化ナトリウムの代わりに同じく塩味を感じる塩化カリウムと呼ばれる物質を使用しています。
この塩化カリウムにはナトリウムが含まれていないため、減塩に役立てることができます。
普段減塩の調味料を使っていないという方は、こういったものに置き換えてみるのもおすすめです。
H3 直前に味付けする
料理をする際は、直前に味付けするようにしましょう。
味がしみこんでいるほうがおいしいからと下味をつけてから調理をする方も多いと思いますが、その場合調味料がしみこみすぎて塩分過多になる可能性が高いです。
そのため、味付けは直前に行い、食材の表面に味がつくようにしましょう。
H3風味を効かせる
だしやスパイスを使って風味を効かせるのも減塩に有効な方法です。
我々が料理を美味しいと感じる要素の中で、味覚以外に嗅覚も大きな役割を担っています。
そのため、だしを効かせたり、コショウやハーブなどのスパイス等を活用することで風味がよくなり、味の薄さが気にならない料理に仕上げることができます。
しかし、顆粒だしや塩コショウなどには塩分が含まれていますので、だしは鰹節や昆布から直接取る、スパイスやハーブは単体のものを活用するようにしましょう。
H3焼き色をつけるなどして香ばしさを
香りや食感をよくするために、焼き色を付けて料理に香ばしさを与えるのも減塩に有用です。
鶏や魚の皮をパリッと焼いてあげるだけでも料理に香ばしさがプラスされ、食欲が増進されます。
また、焼き色をつけるだけならば味の調整が必要ないため、料理が苦手な方でもチャレンジしやすい方法ですね。
H3見た目を整える
味覚、嗅覚以外に視覚も料理のおいしさの一端を担っていますので、料理の見た目を整えることを意識するのも減塩に効果的です。
きれいなお皿を使ったり、盛り付けにこだわることで料理がおいしそうにみえます。
減塩食の味に満足できないからこそ、味以外の要素に力を入れることで楽しく減塩食が継続できます。