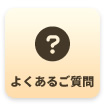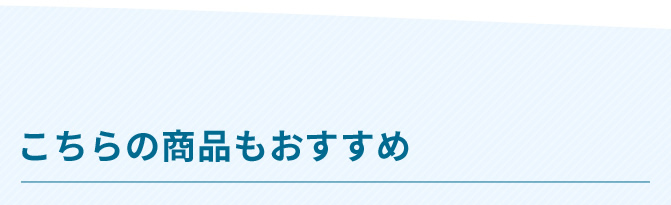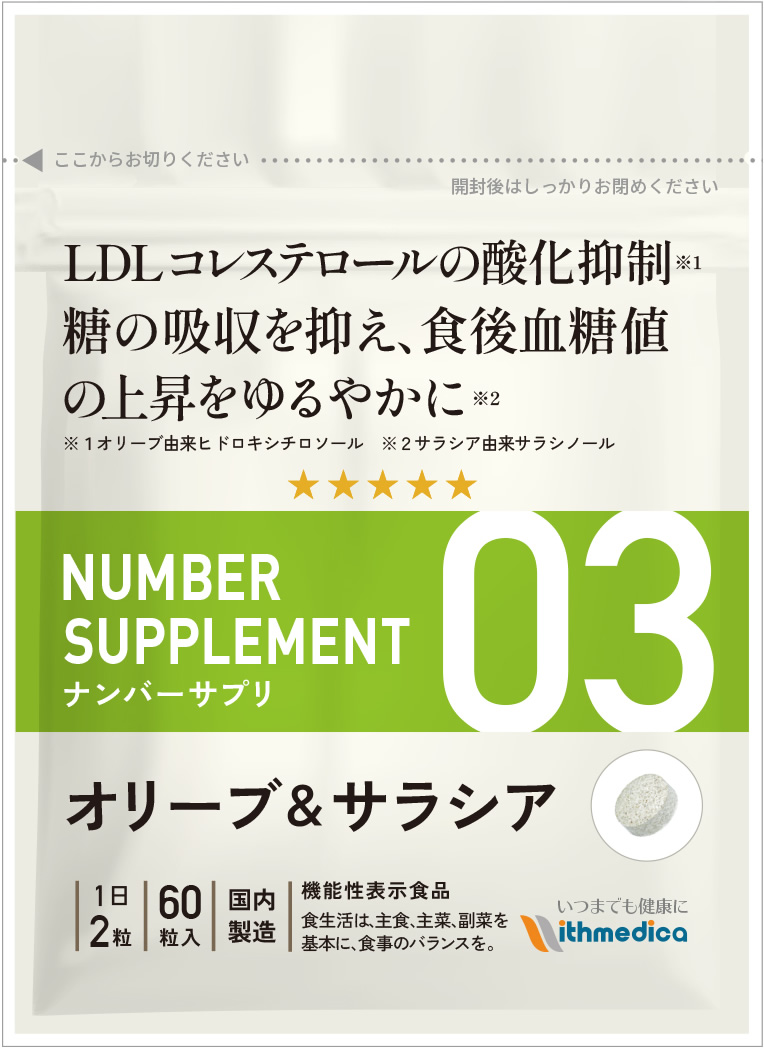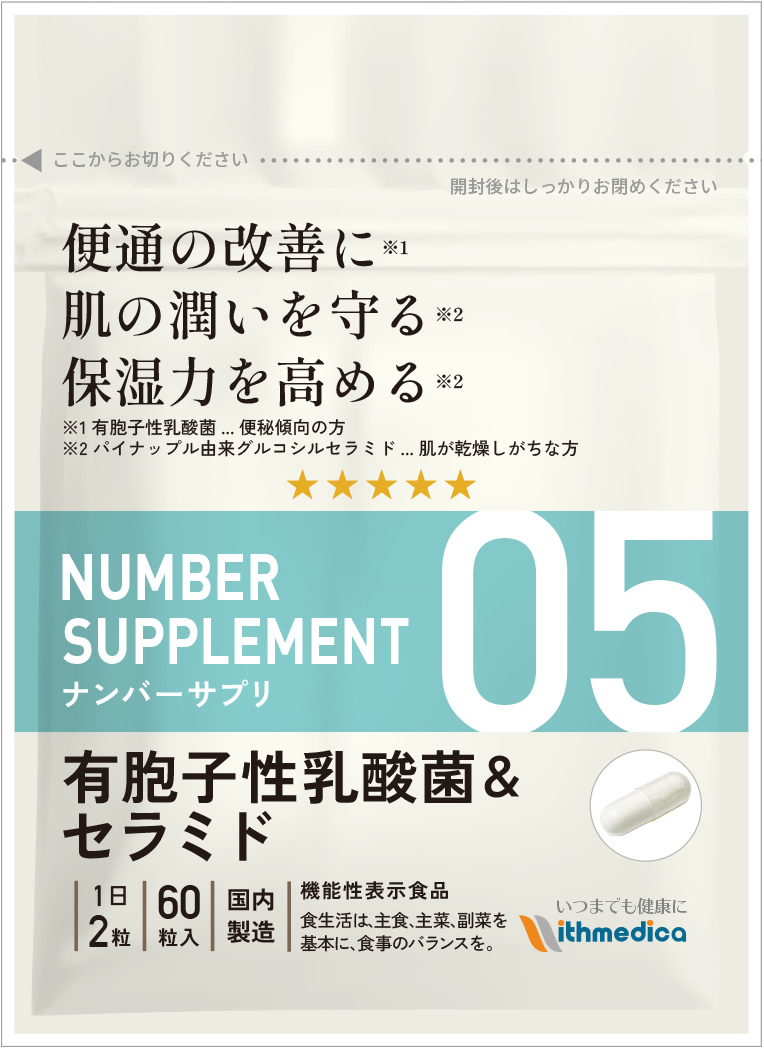実は危険?!高齢者の食欲不振について
執筆者: 岡村珠春(管理栄養士)
[記事公開日] 2023-05-19 [最終更新日] 2023-05-19
高齢者では特に食欲不振のリスクが高くなっています。
その結果、体に必要な栄養が足りなくなり、怪我や病気になりやすくなったり様々な健康リスクが発生します。
今回は食欲不振にならないためにどうしたら良いか、また、なってしまった時の改善方法について紹介していきます。
[ 目次 ]

食欲不振とは
食欲が湧かなく、食事を摂れない状態をいいます。
食欲がなくなると、栄養不足によって身体機能が低下し、それによりさらに食欲が低下する負のサイクルに陥る場合もあります。
食欲がなくなると、栄養不足によって身体機能が低下し、それによりさらに食欲が低下する負のサイクルに陥る場合もあります。

食欲不振になったらどうなるの?
症状:おなかが空かない、食事をする気になれない、食べるものが偏る
身体に必要な栄養を外部から取り込むことが出来ないため、身体に不調が起こりやすくなります。
高齢者に多くみられる症状は主に低栄養、低血糖、脱水の3つです。
【低栄養】
特に高齢者の場合は、栄養が不足すると低栄養状態になる危険があります。
低栄養状態になると、免疫力が落ちたり骨がもろくなったり、皮膚の炎症が起きやすくなり、
褥瘡が発生しやすくなります。
褥瘡が発生すると、消費する栄養量も増加しますが、食欲不振により取り込む栄養が不足しているためますます褥瘡が悪化してしまい治りにくくなるという負のループができてしまいます。
【低血糖】
症状:吐き気、めまい、集中力の低下
食欲不振により、炭水化物が不足することで生じます。
また、糖尿病により血糖値を下げる働きをする薬を飲んでいたり、治療中の方は低血糖を起こしやすくなっています。
このような方は特に注意が必要です。
【脱水】
症状:立ち眩み、倦怠感、微熱、脱力、血圧低下、頻脈、意識障害
普段食事を通して摂取していた水分が摂取できなくなるため、水分不足による脱水状態になります。
身体に必要な栄養を外部から取り込むことが出来ないため、身体に不調が起こりやすくなります。
高齢者に多くみられる症状は主に低栄養、低血糖、脱水の3つです。
【低栄養】
特に高齢者の場合は、栄養が不足すると低栄養状態になる危険があります。
低栄養状態になると、免疫力が落ちたり骨がもろくなったり、皮膚の炎症が起きやすくなり、
褥瘡が発生しやすくなります。
褥瘡が発生すると、消費する栄養量も増加しますが、食欲不振により取り込む栄養が不足しているためますます褥瘡が悪化してしまい治りにくくなるという負のループができてしまいます。
【低血糖】
症状:吐き気、めまい、集中力の低下
食欲不振により、炭水化物が不足することで生じます。
また、糖尿病により血糖値を下げる働きをする薬を飲んでいたり、治療中の方は低血糖を起こしやすくなっています。
このような方は特に注意が必要です。
【脱水】
症状:立ち眩み、倦怠感、微熱、脱力、血圧低下、頻脈、意識障害
普段食事を通して摂取していた水分が摂取できなくなるため、水分不足による脱水状態になります。

食欲不振の原因は?
食欲不振の原因は病気が原因である場合とそうでない場合があります。
<病気が原因の場合>
体の病気と精神の病気の二種類あります。
【体の病気】
病気:風邪、インフルエンザ、消化器官の病気(慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)、がん、心不全、甲状腺機能低下症、誤嚥性肺炎
上記の病気により、食欲不振になることがあります。
また、誤嚥性肺炎は自覚症状がないことも多く注意が必要です。
悪化すると粘膜の感覚が鈍くなってしまい、誤嚥した場合も咳が起こりにくくなるため、肺炎に罹患するリスクが増加してしまいます。
誤嚥性肺炎に気づくためには、食事中のむせや喀痰回数に留意し様子を見ていくことが大切です。
【精神の病気】
病気:うつ病
うつ病に加えて、精神的に病んでいるときに食欲不振になりやすいです。
特に高齢者は身の回りの人の死別や孤独感、生き甲斐がなくなる、
住みなれた自宅や地域から介護施設、病院へ移住することなどによる環境の変化により、精神的に病んでしまうケースが多くみられています。
<病気以外が原因の場合>
【老化】
若いころに比べ、
運動量、筋肉量、基礎代謝が低下し、空腹感がなくなり食欲低下を引き起こします。
また、寝たきりの状態になってしまうと、無気力になり食欲不振を招きます。
【ストレス】
ストレスを感じると自律神経の乱れが生じ、食欲不振になりやすくなります。
身体の不自由さや経済面への不安等により、ストレスを感じる場面が多くあります。
【認知症】
脳の機能が低下し、一人で食事をとることが困難になり、食欲不振につながります。
認知症になると、脳の機能が低下し、食べ物が認識できなくなったり、
食具の使い方がわからなくなったりします。
また、言葉で意思を伝えられない場面が増えていきます。
例えば、「具合が悪くて食べる気が起きない」「口の中が痛くて食べられない」等の意思を伝えることが出来ないことにより、食事への意欲低下がみられます。
認知症は無気力、無関心を引き起こすため食事への興味が薄れていき、食欲不振を起こします。
<病気が原因の場合>
体の病気と精神の病気の二種類あります。
【体の病気】
病気:風邪、インフルエンザ、消化器官の病気(慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など)、がん、心不全、甲状腺機能低下症、誤嚥性肺炎
上記の病気により、食欲不振になることがあります。
また、誤嚥性肺炎は自覚症状がないことも多く注意が必要です。
悪化すると粘膜の感覚が鈍くなってしまい、誤嚥した場合も咳が起こりにくくなるため、肺炎に罹患するリスクが増加してしまいます。
誤嚥性肺炎に気づくためには、食事中のむせや喀痰回数に留意し様子を見ていくことが大切です。
【精神の病気】
病気:うつ病
うつ病に加えて、精神的に病んでいるときに食欲不振になりやすいです。
特に高齢者は身の回りの人の死別や孤独感、生き甲斐がなくなる、
住みなれた自宅や地域から介護施設、病院へ移住することなどによる環境の変化により、精神的に病んでしまうケースが多くみられています。
<病気以外が原因の場合>
【老化】
若いころに比べ、
運動量、筋肉量、基礎代謝が低下し、空腹感がなくなり食欲低下を引き起こします。
また、寝たきりの状態になってしまうと、無気力になり食欲不振を招きます。
【ストレス】
ストレスを感じると自律神経の乱れが生じ、食欲不振になりやすくなります。
身体の不自由さや経済面への不安等により、ストレスを感じる場面が多くあります。
【認知症】
脳の機能が低下し、一人で食事をとることが困難になり、食欲不振につながります。
認知症になると、脳の機能が低下し、食べ物が認識できなくなったり、
食具の使い方がわからなくなったりします。
また、言葉で意思を伝えられない場面が増えていきます。
例えば、「具合が悪くて食べる気が起きない」「口の中が痛くて食べられない」等の意思を伝えることが出来ないことにより、食事への意欲低下がみられます。
認知症は無気力、無関心を引き起こすため食事への興味が薄れていき、食欲不振を起こします。

改善するためには?
その方に合わせて、食べやすいものを食べること、楽しめる食事をすることが大切です。
【食欲不振時に食べやすいもの】
一般的に冷たいものと甘いものは食欲不振時に食べやすいといわれています。代表的にはアイスやプリン、ゼリーが挙げられます。
【楽しめる食事にするためには】
楽しい食卓にするためには、好きな料理や食材を食事に取り入れることは効果的です。
少しでも食べられるものは食べるようにすることで、トリガーとなり、食欲が増進し少しずつ食べられるようになっていきます。
また、食事環境を楽しめるように工夫するのも良いでしょう。
一人での食事ではなく家族や友人とともに会話を楽しみながら召し上がると、脳が刺激を受け食欲増進につながります。
食事自体にも料理方法やメニューに工夫を取り入れることも効果的です。
例えば、季節に合った料理を提供したり、普段と食器を変えたりなど、
味覚のみでなく目でも楽しめるようにすると良いです。
【食欲不振時に食べやすいもの】
一般的に冷たいものと甘いものは食欲不振時に食べやすいといわれています。代表的にはアイスやプリン、ゼリーが挙げられます。
【楽しめる食事にするためには】
楽しい食卓にするためには、好きな料理や食材を食事に取り入れることは効果的です。
少しでも食べられるものは食べるようにすることで、トリガーとなり、食欲が増進し少しずつ食べられるようになっていきます。
また、食事環境を楽しめるように工夫するのも良いでしょう。
一人での食事ではなく家族や友人とともに会話を楽しみながら召し上がると、脳が刺激を受け食欲増進につながります。
食事自体にも料理方法やメニューに工夫を取り入れることも効果的です。
例えば、季節に合った料理を提供したり、普段と食器を変えたりなど、
味覚のみでなく目でも楽しめるようにすると良いです。

まとめ
食欲不振は、様々な原因から発症します。
家族に高齢者に食欲不振がみられた場合は、早急に対策することが大切です。
家族に高齢者に食欲不振がみられた場合は、早急に対策することが大切です。