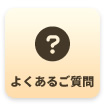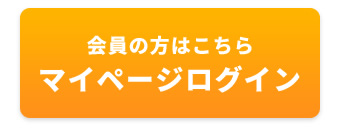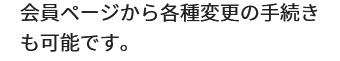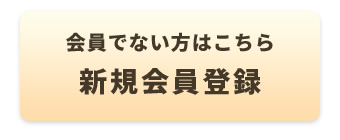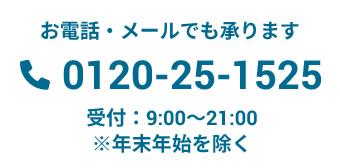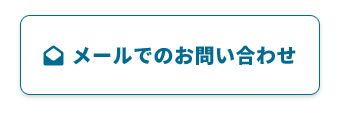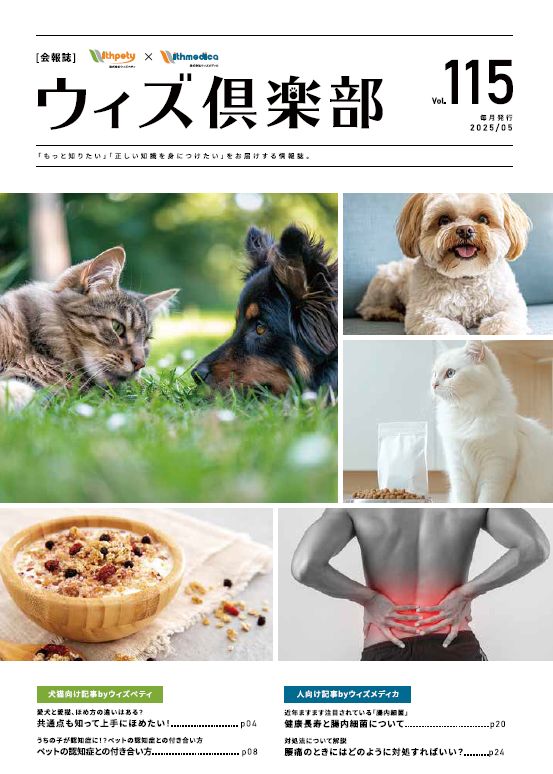健康長寿は「腸内細菌」!?ーー「適切な腸内環境」に必要な生活習慣
執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)
[記事公開日] 2025-03-31 [最終更新日] 2025-04-08
腸を健やかに保つためには、食事だけでなく生活習慣全般を整えること、さらには医療現場における抗菌剤の適正使用が重要となってまいります。腸内環境を最適化するための習慣について、食事と食事以外の両面からチェックしてみましょう。
[ 目次 ]
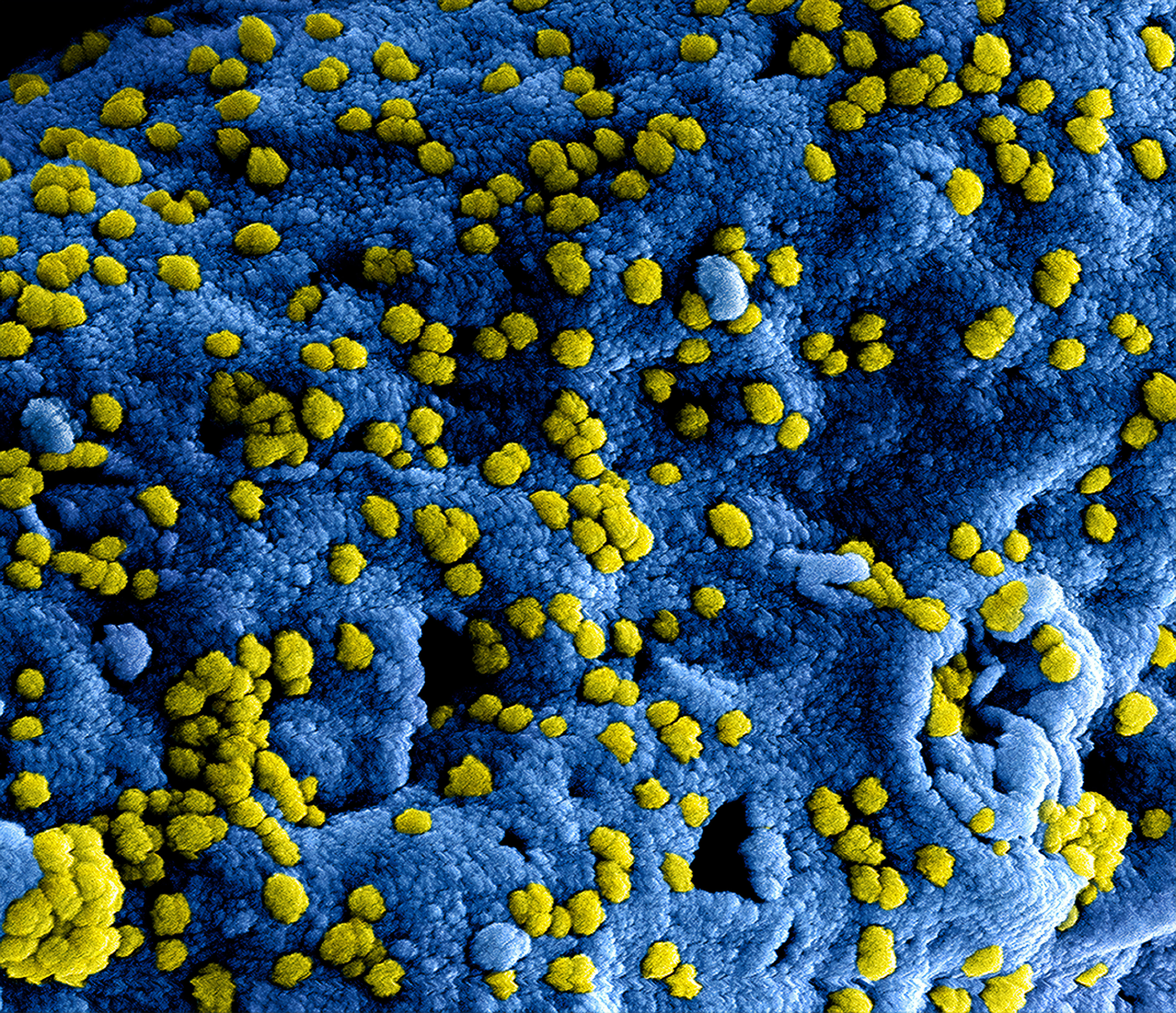
健康長寿と腸内細菌
健康やアンチエイジングに与える影響は非常に大きいとされ、近年ますます注目されてる「腸内細菌」。腸内環境のバランス≒腸内細菌のバランスが崩れることで、免疫力の低下、肌荒れ、肥満、さらにはメンタルヘルスの悪化といった「老化を進める原因」を加速し、さらには特定のがん発症にも関係するのでは?とまで言われています。
腸を健やかに保つためには、食事だけでなく生活習慣全般を整えること、さらには医療現場における抗菌剤の適正使用が重要です。これから腸内環境を最適化するための習慣について、食事と食事以外の両面から解説してまいります。
腸を健やかに保つためには、食事だけでなく生活習慣全般を整えること、さらには医療現場における抗菌剤の適正使用が重要です。これから腸内環境を最適化するための習慣について、食事と食事以外の両面から解説してまいります。
1. 食習慣で腸内「善玉菌」を増やす!
(1) 発酵食品
腸内に善玉菌を増やすことがアンチエイジングに欠かせない言われています。そのカギを握るのが発酵食品。発酵食品には乳酸菌やビフィズス菌など腸内で善玉菌として働く微生物が豊富に含まれており、これらの菌を摂取することで、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)が整いやすくなるのです。
おすすめの発酵食品
・ヨーグルト(プレーン・無糖がベスト)
・納豆
・味噌・漬物(添加物の少ないもの)
・キムチ(乳酸菌が豊富)
・甘酒(ノンアルコールタイプ)
(2) 食物繊維
もう一つ、大切なのが「食物繊維をしっかり摂る」ということです。
食物繊維は腸内細菌のエサとなり、善玉菌を増やすのに役立つといわれています。
水溶性食物繊維(腸内細菌のエサになり、腸内環境を整える)
・オートミール
・もち麦
・りんご
・バナナ
・こんにゃく
・海藻類(わかめ・ひじき)
不溶性食物繊維(腸のぜん動運動を促進し、便通を改善)
・玄米
・豆類
・ごぼう
・さつまいも
・きのこ類
水溶性と不溶性の両方をバランスよく摂ることが重要と言われていますが、それ以前に、そもそも1日あたり十分量の食物繊維がとれていない、というお話もあります。まずはスマホアプリなどを活用し、食事内容を記録してみていただいて、必要十分量の摂取に心がける、というところから始めてみましょう。
(3) 水分
便の水分量が不足すると、腸の動きが鈍くなり、便秘の原因になります。結果、腸内に悪玉菌を増やすことになってしまいます。従い、腸内環境を整えるにあたって、水分補給は欠かせません。
目安: 1日1~1.5Lの水をこまめに飲む
腸内に善玉菌を増やすことがアンチエイジングに欠かせない言われています。そのカギを握るのが発酵食品。発酵食品には乳酸菌やビフィズス菌など腸内で善玉菌として働く微生物が豊富に含まれており、これらの菌を摂取することで、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)が整いやすくなるのです。
おすすめの発酵食品
・ヨーグルト(プレーン・無糖がベスト)
・納豆
・味噌・漬物(添加物の少ないもの)
・キムチ(乳酸菌が豊富)
・甘酒(ノンアルコールタイプ)
(2) 食物繊維
もう一つ、大切なのが「食物繊維をしっかり摂る」ということです。
食物繊維は腸内細菌のエサとなり、善玉菌を増やすのに役立つといわれています。
水溶性食物繊維(腸内細菌のエサになり、腸内環境を整える)
・オートミール
・もち麦
・りんご
・バナナ
・こんにゃく
・海藻類(わかめ・ひじき)
不溶性食物繊維(腸のぜん動運動を促進し、便通を改善)
・玄米
・豆類
・ごぼう
・さつまいも
・きのこ類
水溶性と不溶性の両方をバランスよく摂ることが重要と言われていますが、それ以前に、そもそも1日あたり十分量の食物繊維がとれていない、というお話もあります。まずはスマホアプリなどを活用し、食事内容を記録してみていただいて、必要十分量の摂取に心がける、というところから始めてみましょう。
(3) 水分
便の水分量が不足すると、腸の動きが鈍くなり、便秘の原因になります。結果、腸内に悪玉菌を増やすことになってしまいます。従い、腸内環境を整えるにあたって、水分補給は欠かせません。
目安: 1日1~1.5Lの水をこまめに飲む

2. 食事以外で腸内環境を整える生活習慣
(1) 良質な睡眠を確保する
「食事と睡眠」これらは必ずペアで考えるべきものです。睡眠の質の低下は、言うまでもなく、腸内細菌のバランスを崩し、腸の働きを低下させる要因となりえます。ストレスや不規則な睡眠は当然のことながら腸内環境に悪影響を与えます。
良質な睡眠のため、ここだけは押さえる!ポイントはこちらの3つ。
・睡眠2時間前までにぬるめのお風呂に入る(38〜40℃のお湯に10〜15分)
・眠る1時間前にスマホやPCを控える
・毎日同じ時間に寝起きする
(2) 適度な運動を取り入れる
喋ることができる程度の強さで一日合計20分。適度な運動習慣は良質な睡眠につながり、腸の動きを活性化させる効果があります。ヨガやピラティスは腸のぜん動運動を促進し、便秘解消に役立つことも…!
おすすめの運動
・ウォーキング(できれば坂道や階段の上り下りも取り入れて)
・ヨガ・ストレッチ(腸を刺激する「ねじりのポーズ」など)
・軽い筋トレ(スクワットなど)
テキパキと、家事やお部屋のお掃除も運動になりますよ!
まとめて20分取る必要はなく、「合計」で20分になればOKです。どうでしょう、これなら実践できそうではないでしょうか?
(3) ストレスと上手に向き合う
実はストレスは「適度」が◎。溜まりすぎても交感神経が優位になり、腸の働きが低下しますが、「ストレスがなさすぎ」もダメなんです。適度に緊張し、適度にリラックスすることで交感神経・副交感神経がそれぞれ程よく活性化し、腸内環境が整いやすくなります。
(4) 抗生物質の乱用を避ける
かねてから「抗菌剤をもらいに病院に行くことが“安心”」という、日本人特有の心理文化を背景に、「ちょっと喉が痛いから」「風邪っぽいから」と、まるで万能薬のように抗生物質を欲しがることが問題視されています。というのも、抗生物質は腸内の善玉菌・悪玉菌を問わず根こそぎ一掃してしまうのです...! 結果、腸内環境が荒れ放題になり、かえって免疫力が低下することも。やむを得ず服用する場合は、プロバイオティクス(乳酸菌・ビフィズス菌)を併用し、腸のリカバリーを忘れずに行いたいところです。
「食事と睡眠」これらは必ずペアで考えるべきものです。睡眠の質の低下は、言うまでもなく、腸内細菌のバランスを崩し、腸の働きを低下させる要因となりえます。ストレスや不規則な睡眠は当然のことながら腸内環境に悪影響を与えます。
良質な睡眠のため、ここだけは押さえる!ポイントはこちらの3つ。
・睡眠2時間前までにぬるめのお風呂に入る(38〜40℃のお湯に10〜15分)
・眠る1時間前にスマホやPCを控える
・毎日同じ時間に寝起きする
(2) 適度な運動を取り入れる
喋ることができる程度の強さで一日合計20分。適度な運動習慣は良質な睡眠につながり、腸の動きを活性化させる効果があります。ヨガやピラティスは腸のぜん動運動を促進し、便秘解消に役立つことも…!
おすすめの運動
・ウォーキング(できれば坂道や階段の上り下りも取り入れて)
・ヨガ・ストレッチ(腸を刺激する「ねじりのポーズ」など)
・軽い筋トレ(スクワットなど)
テキパキと、家事やお部屋のお掃除も運動になりますよ!
まとめて20分取る必要はなく、「合計」で20分になればOKです。どうでしょう、これなら実践できそうではないでしょうか?
(3) ストレスと上手に向き合う
実はストレスは「適度」が◎。溜まりすぎても交感神経が優位になり、腸の働きが低下しますが、「ストレスがなさすぎ」もダメなんです。適度に緊張し、適度にリラックスすることで交感神経・副交感神経がそれぞれ程よく活性化し、腸内環境が整いやすくなります。
(4) 抗生物質の乱用を避ける
かねてから「抗菌剤をもらいに病院に行くことが“安心”」という、日本人特有の心理文化を背景に、「ちょっと喉が痛いから」「風邪っぽいから」と、まるで万能薬のように抗生物質を欲しがることが問題視されています。というのも、抗生物質は腸内の善玉菌・悪玉菌を問わず根こそぎ一掃してしまうのです...! 結果、腸内環境が荒れ放題になり、かえって免疫力が低下することも。やむを得ず服用する場合は、プロバイオティクス(乳酸菌・ビフィズス菌)を併用し、腸のリカバリーを忘れずに行いたいところです。

まずは「ついサボりがち」あの習慣から!
腸内環境を整えるためには、まずは食事と睡眠、その他にも生活習慣上のあらゆる面からアプローチすることが大切であり、24時間の行いすべてが関係してきます。
これらを正すため、実は特にこれといって新しいことを始める、などではなく、今まで「やらなければなあ、と思ってついやり過ごしたこと」にヒントがあることがほとんど。
日々の小さな習慣の見直し、そして積み重ねが、腸を健やかに保つカギとなります。まずはできることから始めてみませんか?
これらを正すため、実は特にこれといって新しいことを始める、などではなく、今まで「やらなければなあ、と思ってついやり過ごしたこと」にヒントがあることがほとんど。
日々の小さな習慣の見直し、そして積み重ねが、腸を健やかに保つカギとなります。まずはできることから始めてみませんか?