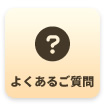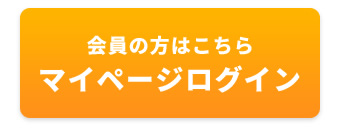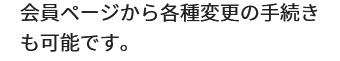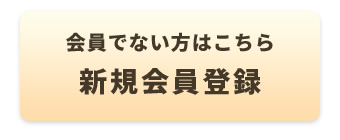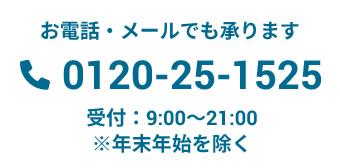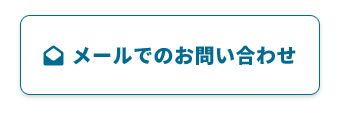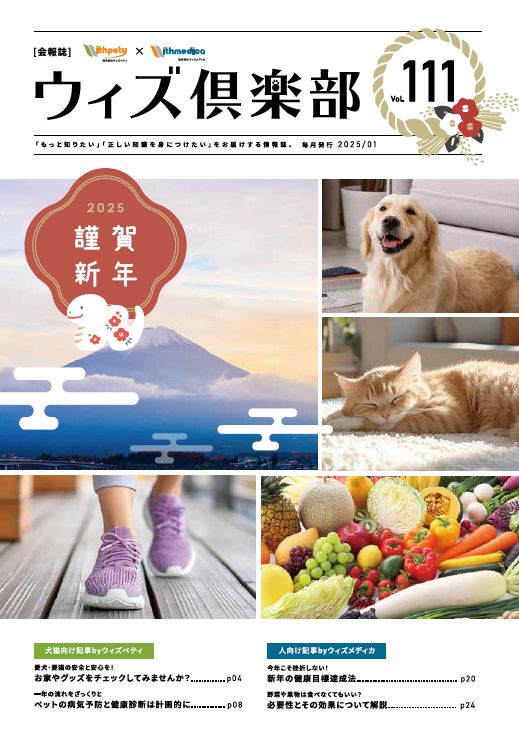今年こそ挫折しない!新年の健康目標達成法
執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)
[記事公開日] 2024-11-28 [最終更新日] 2025-01-07
[ 目次 ]

やらねばいけないことはわかっているのだけれども…
新年は、新たな気持ちで健康を見直し、目標を立てる絶好の機会です。しかし、多くの人が新年の健康目標を立てても、達成しきれず挫折してしまうことが少なくありません。その原因の多くが「やらなきゃいけないことはわかっているに、続かない。」一つ決めたことをいかに習慣化していくか、これが難しいのです。
今まで幾度となく挫折してきた「新年の健康目標」、今年こそ達成したいですよね。この機会に目標に向かって行動を続けるための効果的な方法を考えてみましょう。
今まで幾度となく挫折してきた「新年の健康目標」、今年こそ達成したいですよね。この機会に目標に向かって行動を続けるための効果的な方法を考えてみましょう。
0. 具体的なプランを立てる
漠然と「健康的になる」という目標を立てても、具体性がないために行動に移すのが難しくなります。「座り作業中1時間に1回は立つようにする」「野菜から食べ始めるようにする」といった、明確な行動計画を立てることが、目標達成への近道です。
1. 「今からすぐにでもできそうな目標」を設定する
自分の生活スタイルや現在の健康状態に合った現実的な目標を設定し「今からでも始める」その結果「明日は少しだけ進歩した自分になっている」ことがポイントです。「今日はいいや、明日から」と繰り越してしまうことで、明日まで現状維持になってしまう。これが365日続いてしまえば「今年も目標達成ならず」となってしまいます。しかし「明日ジムにいく用意だけしておく(明日になって行きたくならないかもしれないけど)」といったことであっても、実践すれば、少なくとも翌日の状況は、少しだけ前進した状態となります。この積み重ねが「とっかかり」となります。
運動を始めたばかりの人が、いきなり「週に5日ジムに通う」「フルマラソンを走る」と言ったことを目標にしてしまうから、達成が難しく、挫折しやすくなってしまうわけです。まずは「1日1回は駅のエスカレーターを使わず階段を上る」などといった、このくらいだったらやれそう、というくらいの小さな目標を立てて、それを達成することで自信をつけていくことが大事なのです。
運動を始めたばかりの人が、いきなり「週に5日ジムに通う」「フルマラソンを走る」と言ったことを目標にしてしまうから、達成が難しく、挫折しやすくなってしまうわけです。まずは「1日1回は駅のエスカレーターを使わず階段を上る」などといった、このくらいだったらやれそう、というくらいの小さな目標を立てて、それを達成することで自信をつけていくことが大事なのです。
3. スモールステップを意識し、まずは28日チャレンジ!
よく歯磨きの習慣を例に出すことが多いのですが、毎日歯を磨くことが続かずに挫折してしまう、という方はほとんどいないかと思うのです。これは、小さい頃、最初は意識的に行動を続けることで、大人になって、気づいたら毎晩歯を磨いて寝るというふうに「自動化」されるようになっているわけです。
一度に多くのことを変え、当たり前のように続けようとするから、負担が大きくなってやめてしまうわけですので、変化量を少なくし、まずは1週間やってみよう、それができたら1ヶ月、2ヶ月…徐々に広げていけばいいのです。1ヶ月継続できた、ともなるとそれなりの自信がついてきます。
「毎朝、とりあえず玄関で運動靴を履く」とかでもいいです。そこから、外に出て深呼吸をする、家の周りを一周する、そこから徐々に距離を時間を延ばしていくなど、小さなステップを踏んで習慣を定着させましょう。
一度に多くのことを変え、当たり前のように続けようとするから、負担が大きくなってやめてしまうわけですので、変化量を少なくし、まずは1週間やってみよう、それができたら1ヶ月、2ヶ月…徐々に広げていけばいいのです。1ヶ月継続できた、ともなるとそれなりの自信がついてきます。
「毎朝、とりあえず玄関で運動靴を履く」とかでもいいです。そこから、外に出て深呼吸をする、家の周りを一周する、そこから徐々に距離を時間を延ばしていくなど、小さなステップを踏んで習慣を定着させましょう。

4. 習慣化を目指す…モチベーションを保つための工夫
一説によると、こうして新しく始めたことが習慣化するまでの平均日数は66日なのだそうです。ともすると、3ヶ月続いたものは、そのまま習慣化できる可能性が高まります。だからこその、まずは1ヶ月チャレンジ、なのですが、目標達成のためにはモチベーションの維持が不可欠です。鹿日、モチベーションが高い時に立てた目標を、そのモチベーションが高いまま続くことを前提にことを進めると、挫折します。「仮に、疲れた時でも、実践できそうか」吟味したり、「モチベーションが下がった時のプランB」を考えてみたりするのが良いのです。
体調不良や忙しい日々など、思い通りに進まない、計画通りにいかないことは「必ずある」として計画を進めるのがポイントです。「週3回、1時間の運動を目標にしていたが、無理なときは1日5分を7日間でも回でもいいか」といった、柔軟な対応ができるようにしておきましょう。小さな失敗があっても、自分を責めるのではなく「とにかく今の自分にできる限り、わずかでも前に進むことが大切」と前向きに考えることが成功の秘訣です。
仮にモチベーションが3割に落ちたとしても、その3割の中で100%が出せれば良いのです。最終目標は「健康的な生活を送りたい」「体力をつけて旅行を楽しみたい」であったとしたら、そのために、今日より明日、少しでも前進していれば、目標達成に近づくわけですから。
体調不良や忙しい日々など、思い通りに進まない、計画通りにいかないことは「必ずある」として計画を進めるのがポイントです。「週3回、1時間の運動を目標にしていたが、無理なときは1日5分を7日間でも回でもいいか」といった、柔軟な対応ができるようにしておきましょう。小さな失敗があっても、自分を責めるのではなく「とにかく今の自分にできる限り、わずかでも前に進むことが大切」と前向きに考えることが成功の秘訣です。
仮にモチベーションが3割に落ちたとしても、その3割の中で100%が出せれば良いのです。最終目標は「健康的な生活を送りたい」「体力をつけて旅行を楽しみたい」であったとしたら、そのために、今日より明日、少しでも前進していれば、目標達成に近づくわけですから。

5. 他者を巻き込む
友人や家族と目標を共有し、一緒に取り組むことも効果的です。サポートし合える仲間がいると、モチベーションを保ちやすくなります。SNSを通じて日々の進捗を報告したり…「道連れ」となる仲間を見つけたりするのも良いアイデアです。

6. 成功を祝う
こうして、わずかながらも、今日の自分より、翌日の自分に進捗があった時は、自分を褒めることを忘れないようにしましょう。「目標が達成できなかった」「モチベーションが保てなかった」自分を責めるのではなく「モチベーションが低いなりの対処ができた」自分を褒めてあげる、このマインドです。小さな目標を達成するたびに、ちょっとしたご褒美を用意するのもいいですね。

まずは今日の一歩から!
新年は、心機一転して新たな健康目標に挑戦する良いタイミングです。ほんのわずかな目標で良いのです。小さなステップを踏んで習慣化し、モチベーションの変化に対応しながら、今日より明日、この姿勢でわずかでも前に進む。長期的な成功を手に入れている人が必ずやっていることです。新年をより健やかに、充実したものにするために、まずは小さな一歩から始めてみましょう。