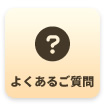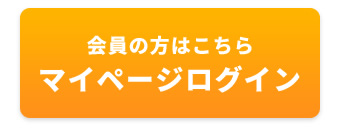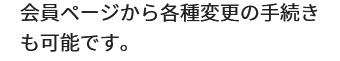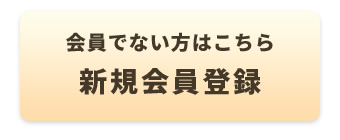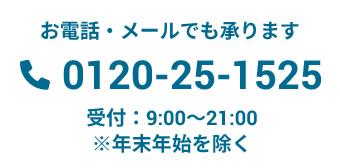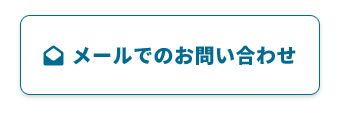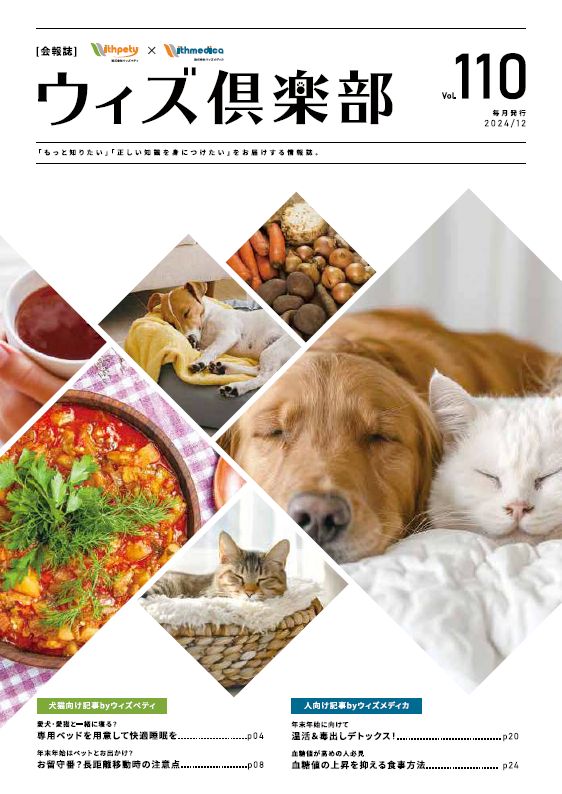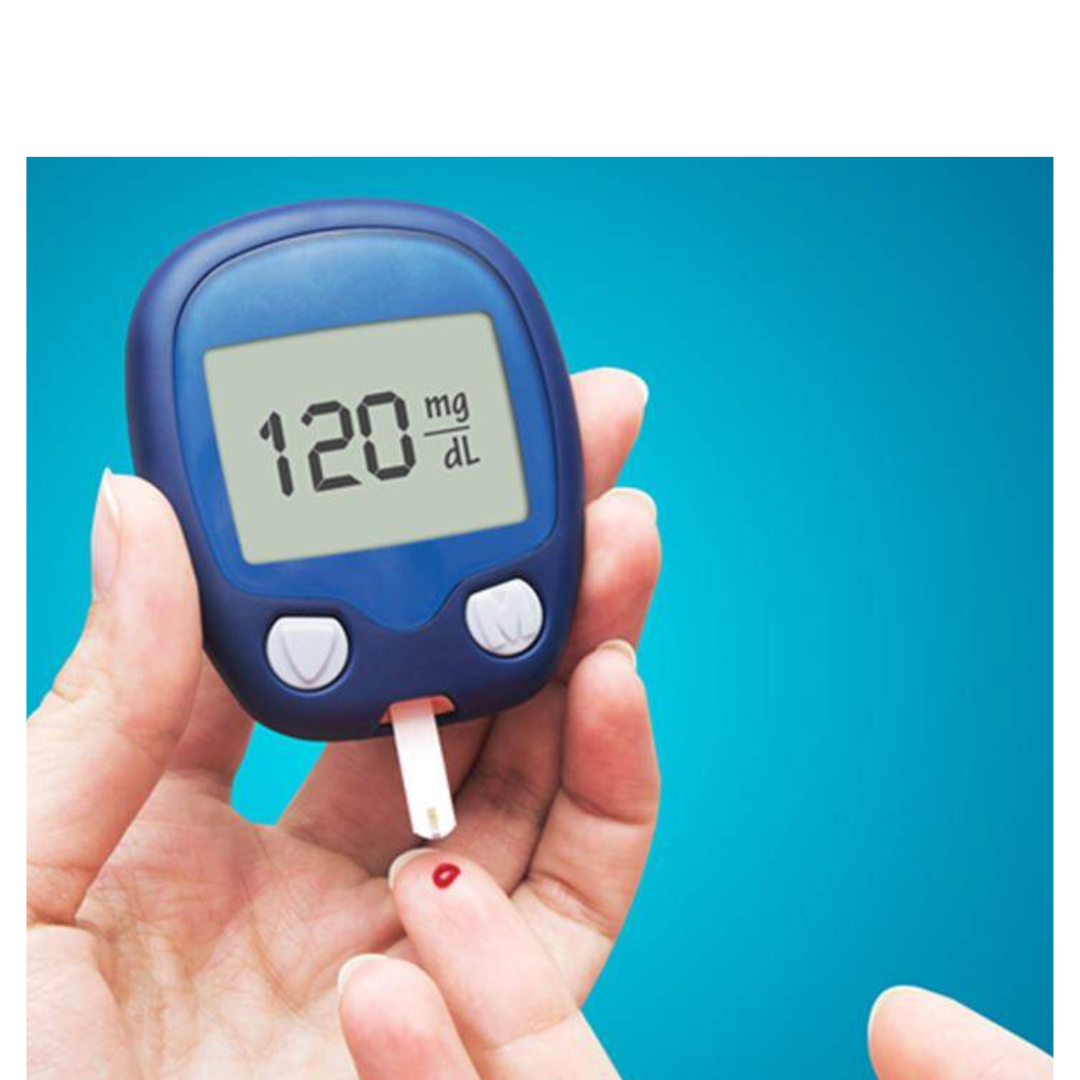年末年始に向けて温活&毒出しデトックス!
執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)
[記事公開日] 2024-10-31 [最終更新日] 2024-11-05
[ 目次 ]

1年の締めくくりに温活と毒出し=デトックス!
1年が過ぎるのも早いもので、そろそろお正月休みですね。寒さが厳しくなり、身体の冷えを感じる年末年始休みに備えて冷えやむくみを解消し、体調を整える「温活」で、今年の厄を「デトックス」! 元気に新年を迎えようではありませんか。今月は、食事や運動、日常生活で心がけたい温活&デトックス習慣について詳しくご紹介いたします。
温活の基本は食事から!!
温活によるデトックスの目的は、身体を温めることで血行を良くし、代謝を高めて老廃物を排出しやすくすることです。
何よりもの基本は、身体を温める食事です。体温が上がることで血行が良くなり、新陳代謝が活性化され、老廃物を排出しやすくなりますので、身体を内側から温める「温め食材」は積極的に摂りたいところなのです。体の冷えを解消するために、日々の食事に身体を温める食材を取り入れることから始めましょう。
おすすめの食材は、根菜類やスパイス、発酵食品。これらの食材には身体を温める効果がありますので積極的に取り入れていきましょう。
根菜類:にんじん、ごぼう、れんこん、かぼちゃ、さつまいもなど
スパイス:しょうが、シナモン、唐辛子など
発酵食品:味噌、納豆、キムチ、ヨーグルトなど
体を芯から温めてくれる根菜類は、特に煮物やスープにして摂取すると、効率的に体を芯から温めることができます。スパイスには、体を温め、代謝を高める効果があります。しょうがは、生姜湯やスープも良いですし、炒め物に加えていただいてもいいですね。発酵食品は、腸内環境を整えるのみならず、体を温める効果があるのです。発酵食品といえば…日本人には味噌汁があるではないですか! 毎日の食事に積極的に取り入れてまいりましょう。
冷たい飲み物の飲み過ぎにも気をつけることが大事です。冷たい飲み物を避け、温かい飲み物を意識的に摂ることで、内臓から体を温めたいところ。まずは朝起きたときに一杯の白湯を飲む習慣から! 胃腸が温め、老廃物の排出がスムーズにしてくれます。
その先の応用編として、しょうが湯ハーブティーなどはいかがでしょうか。はちみつを加えて飲むのもいいですね。
何よりもの基本は、身体を温める食事です。体温が上がることで血行が良くなり、新陳代謝が活性化され、老廃物を排出しやすくなりますので、身体を内側から温める「温め食材」は積極的に摂りたいところなのです。体の冷えを解消するために、日々の食事に身体を温める食材を取り入れることから始めましょう。
おすすめの食材は、根菜類やスパイス、発酵食品。これらの食材には身体を温める効果がありますので積極的に取り入れていきましょう。
根菜類:にんじん、ごぼう、れんこん、かぼちゃ、さつまいもなど
スパイス:しょうが、シナモン、唐辛子など
発酵食品:味噌、納豆、キムチ、ヨーグルトなど
体を芯から温めてくれる根菜類は、特に煮物やスープにして摂取すると、効率的に体を芯から温めることができます。スパイスには、体を温め、代謝を高める効果があります。しょうがは、生姜湯やスープも良いですし、炒め物に加えていただいてもいいですね。発酵食品は、腸内環境を整えるのみならず、体を温める効果があるのです。発酵食品といえば…日本人には味噌汁があるではないですか! 毎日の食事に積極的に取り入れてまいりましょう。
冷たい飲み物の飲み過ぎにも気をつけることが大事です。冷たい飲み物を避け、温かい飲み物を意識的に摂ることで、内臓から体を温めたいところ。まずは朝起きたときに一杯の白湯を飲む習慣から! 胃腸が温め、老廃物の排出がスムーズにしてくれます。
その先の応用編として、しょうが湯ハーブティーなどはいかがでしょうか。はちみつを加えて飲むのもいいですね。

生活面で気をつけたいところ
日々の生活の中で、小さな工夫を積み重ねることで、体を温める習慣が身につき、デトックス効果が高まります。
まず何より首、手首、足首の「三つの首」を冷やさないこと。この三つの部位を温めることで体全体の血行が良くなり、冷えを感じにくくなります。マフラーや手袋、レッグウォーマーなどを活用し、外出時に冷えないように工夫しましょう。筆者のおすすめは夏は涼しく、冬は暖かい、シルクの長所を生かした温活グッズです。シルクソックス、シルクのレッグウォーマーなど、手軽に取り入れられる温活アイテムが手放せません。ぜひ試してみてください。
デスクワークや長時間の座り仕事は、血行が滞り、冷えを感じやすくなります。1時間に1度は席を立って軽く体を動かすようにしましょう。トイレに行くのもそうですが、足踏みをしたり、肩を回したりするだけでもOKです。体が温まり、血行が良くなります。
まず何より首、手首、足首の「三つの首」を冷やさないこと。この三つの部位を温めることで体全体の血行が良くなり、冷えを感じにくくなります。マフラーや手袋、レッグウォーマーなどを活用し、外出時に冷えないように工夫しましょう。筆者のおすすめは夏は涼しく、冬は暖かい、シルクの長所を生かした温活グッズです。シルクソックス、シルクのレッグウォーマーなど、手軽に取り入れられる温活アイテムが手放せません。ぜひ試してみてください。
デスクワークや長時間の座り仕事は、血行が滞り、冷えを感じやすくなります。1時間に1度は席を立って軽く体を動かすようにしましょう。トイレに行くのもそうですが、足踏みをしたり、肩を回したりするだけでもOKです。体が温まり、血行が良くなります。

適度な運動は不可欠です
運動をすることで血行が良くなり、体全体が温まることは言うまでもなく、適度な筋肉の増強は、基礎代謝そのものを上げてくれます。
ウォーキングやジョギング、ダンスなどの有酸素運動、ダンベル運動、ピラティス、スクワットなどの筋力を上げるトレーニングをうまく組み合わせて行うのが理想です。家でキビキビと家事をすることも運動になります。一気にではなく、分けて行ってもOKですので、1日20分は確保したいところです。
運動後の「ゆるめる」動きも大事です。ヨガやストレッチは、体をゆっくり動かすことで血行を促進し、体を温める効果があります。特に、骨盤周りや足先のストレッチは、血行が滞りやすい部分の冷えを解消するのに効果的です。筆者が心がけているおが寝る前の5分ヨガ。1日の疲れをリセットし、リラックス効果も得られ、ぐっすりと眠ることができます。
ウォーキングやジョギング、ダンスなどの有酸素運動、ダンベル運動、ピラティス、スクワットなどの筋力を上げるトレーニングをうまく組み合わせて行うのが理想です。家でキビキビと家事をすることも運動になります。一気にではなく、分けて行ってもOKですので、1日20分は確保したいところです。
運動後の「ゆるめる」動きも大事です。ヨガやストレッチは、体をゆっくり動かすことで血行を促進し、体を温める効果があります。特に、骨盤周りや足先のストレッチは、血行が滞りやすい部分の冷えを解消するのに効果的です。筆者が心がけているおが寝る前の5分ヨガ。1日の疲れをリセットし、リラックス効果も得られ、ぐっすりと眠ることができます。

お風呂でしっかり温まることも忘れずに
温活に欠かせないのが、入浴です。シャワーのみで済まさず、浴槽に入ってください。38~40度のぬるめのお湯に15~20分ほど浸かると、血行が良くなり、老廃物を排出しやすくなります。体が芯から温まります。また、入浴剤やバスソルトを入れると、さらに効果が高まります。
胸の下あたりまでお湯に浸かる半身浴は、心臓への負担が少なく、長時間温まることができます。肩まわりが寒いとお感じの場合は、肩にタオルをかければ解決です。
お風呂で温まった後は、肌の水分が失われやすいため、しっかりと保湿を行いましょう。お風呂から出て5分以内に行うことがポイントです。保湿クリームでマッサージをするのもいいですね。
胸の下あたりまでお湯に浸かる半身浴は、心臓への負担が少なく、長時間温まることができます。肩まわりが寒いとお感じの場合は、肩にタオルをかければ解決です。
お風呂で温まった後は、肌の水分が失われやすいため、しっかりと保湿を行いましょう。お風呂から出て5分以内に行うことがポイントです。保湿クリームでマッサージをするのもいいですね。

まとめ
年末年始を迎えるにあたり、食事、運動、日常生活の工夫をバランス良く取り入れていきたいところ。温め食材を摂り、温かい飲み物で内側から体を温め、適度な運動や入浴で血行を促進し、さらに衣類や生活習慣で冷えを防ぐことで、温活&デトックス効果が高まります。ぜひとも実践いただき、冷え知らずの健康な体で年末年始を迎えようではありませんか。