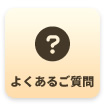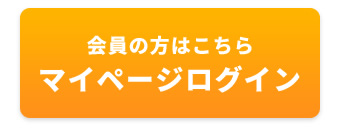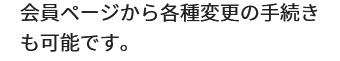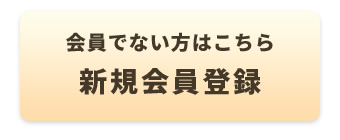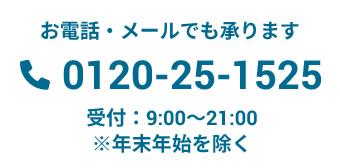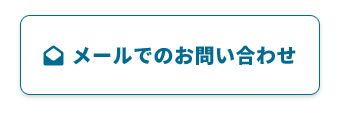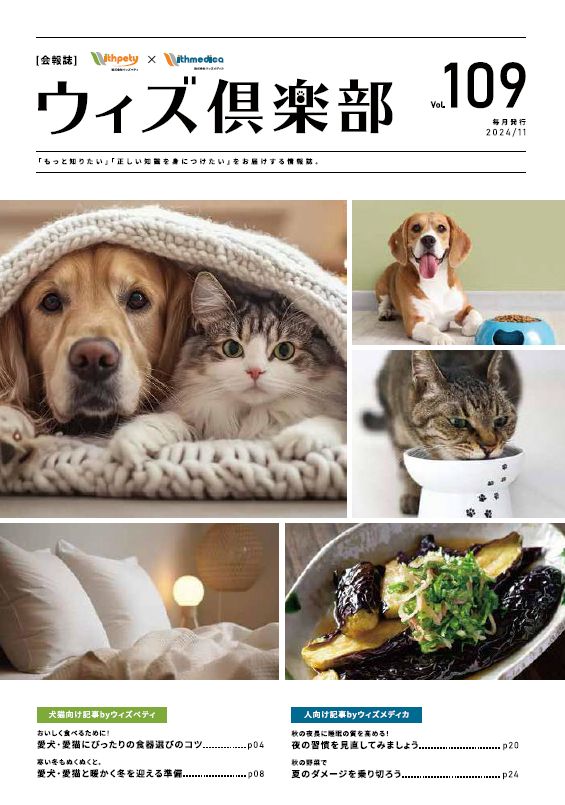秋の夜長に睡眠の質を高める!夜の習慣を見直してみましょう
執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)
[記事公開日] 2024-09-29 [最終更新日] 2024-10-03
[ 目次 ]

健康の維持には良質な睡眠が不可欠!
睡眠は「質」が大事…よく耳にしますよね。しかし、質の良い睡眠とは、単に長い時間眠ることではありません。大事なのは「深く」、「十分に」、「規則的に」眠ること。睡眠の長さだけではなく、その中でいかに深い眠りを確保できるかが重要です。
質の良い睡眠を得ることで、心身の疲労回復、免疫力の向上、肌の活性化、集中力や記憶力の向上など、さまざまな健康効果が期待できます。さらに、アンチエイジングにも効果があり、健康や美しさ、そして精神的な若さを保つために不可欠なものです。
しかし、現代社会において、私たちは日々多くのストレスや情報に晒されており、睡眠の質が低下しがちです。
秋の夜長は、意識的に睡眠の質を高める良いタイミング。睡眠の質を向上させるためには「寝る前の時間」を適切に過ごし、それを「習慣化」することで、自分に合った「ナイトタイムルーティン」を確立していくことが大事です。(※ナイトタイムルーティン=寝る前に行う一連の活動や習慣)
睡眠不足や質の悪い睡眠は、肥満や糖尿病、心臓病などのリスクを高めるだけでなく、認知機能の低下などの精神的な問題を引き起こす可能性もあります。この機会にぜひ毎晩の「ナイトタイムルーティン」を見直し、良質な睡眠を手に入れましょう!
質の良い睡眠を得ることで、心身の疲労回復、免疫力の向上、肌の活性化、集中力や記憶力の向上など、さまざまな健康効果が期待できます。さらに、アンチエイジングにも効果があり、健康や美しさ、そして精神的な若さを保つために不可欠なものです。
しかし、現代社会において、私たちは日々多くのストレスや情報に晒されており、睡眠の質が低下しがちです。
秋の夜長は、意識的に睡眠の質を高める良いタイミング。睡眠の質を向上させるためには「寝る前の時間」を適切に過ごし、それを「習慣化」することで、自分に合った「ナイトタイムルーティン」を確立していくことが大事です。(※ナイトタイムルーティン=寝る前に行う一連の活動や習慣)
睡眠不足や質の悪い睡眠は、肥満や糖尿病、心臓病などのリスクを高めるだけでなく、認知機能の低下などの精神的な問題を引き起こす可能性もあります。この機会にぜひ毎晩の「ナイトタイムルーティン」を見直し、良質な睡眠を手に入れましょう!

1. なるべく決まった時間に寝る
睡眠の質を上げるには、体内時計(サーカディアンリズム)を乱さないことが大切です。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるように心がけましょう。規則的な睡眠パターンを保つことで、自然と眠くなるタイミングを体が覚え、入眠がスムーズになります。
週末でも、睡眠時間を大幅にずらさないように注意したいところです。寝だめの許容範囲は2時間以内、できれば1時間以内が理想的とされています。2時間以内のズレであれば、体内時計を大きく乱すことなくリセットできます。
週末でも、睡眠時間を大幅にずらさないように注意したいところです。寝だめの許容範囲は2時間以内、できれば1時間以内が理想的とされています。2時間以内のズレであれば、体内時計を大きく乱すことなくリセットできます。

2. 寝る2時間前に「お風呂」
就寝前の1〜2時間はリラックスする時間にしましょう。日本人に深く浸透する習慣の一つに「温かいお風呂に浸かる」というものがありますね。実は入浴によって体温が一時的に上昇し、その後、体温が下がっていく過程で自然と眠気が生じます。
寝る直前にお風呂に入り、体温が高いままで寝つきにくかった経験はありませんか?これは、体温が下がらないとスムーズに入眠できないためです。そのため、寝る2時間前くらいにお風呂から上がり、体温が徐々に下がっていくタイミングで布団に入るのが理想的です。
では、お風呂から上がった後、寝るまでの時間はどう過ごせば良いでしょうか。
寝る直前にお風呂に入り、体温が高いままで寝つきにくかった経験はありませんか?これは、体温が下がらないとスムーズに入眠できないためです。そのため、寝る2時間前くらいにお風呂から上がり、体温が徐々に下がっていくタイミングで布団に入るのが理想的です。
では、お風呂から上がった後、寝るまでの時間はどう過ごせば良いでしょうか。
3. 適切な照明を選ぶ
照明は睡眠の質に大きく影響します。夜は部屋の明かりを暗くし、柔らかな暖色系の照明を使用するのがおすすめです。明るすぎる照明は、体が「昼である」と勘違いし、覚醒を促してしまいます。暗くすることで体に「夜である」という信号を送り、睡眠の準備を整えることができます。
余談ですが、高級ホテルでは、窓が大きく、照明が少なめで、昼は自然光を取り入れ、夜は照明が暗めに設計されていることが多いですよね。これは、こうした事実に基づいているのではないかと筆者は考えています。
余談ですが、高級ホテルでは、窓が大きく、照明が少なめで、昼は自然光を取り入れ、夜は照明が暗めに設計されていることが多いですよね。これは、こうした事実に基づいているのではないかと筆者は考えています。
4. ブルーライトの影響を避ける
照明の話に続けて、スマートフォンやパソコン、テレビなどの電子機器が発するブルーライトにも注意しましょう。ブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、眠気を妨げる原因となります。就寝前の1時間は、これらの電子機器の使用を控えるのが理想的です。
とはいえ、パソコンやスマホでの作業が日常化している方も多いかと思います。そんな場合は、ブルーライトカットの眼鏡を使用したり、デバイスの夜間モードを活用するのがおすすめです。
また、ブルーライトを避けるために、紙の書籍を読んだり、音楽を聴くのも効果的です。最近は紙の書籍を手に取る機会が減り、本屋さんも少なくなりましたが、筆者はあえての「紙媒体」を意識的に活用、夜寝る前は紙媒体のテキストを使用して韓国語の勉強をすなどして、ブルーライトを回避するよう努めています。
とはいえ、パソコンやスマホでの作業が日常化している方も多いかと思います。そんな場合は、ブルーライトカットの眼鏡を使用したり、デバイスの夜間モードを活用するのがおすすめです。
また、ブルーライトを避けるために、紙の書籍を読んだり、音楽を聴くのも効果的です。最近は紙の書籍を手に取る機会が減り、本屋さんも少なくなりましたが、筆者はあえての「紙媒体」を意識的に活用、夜寝る前は紙媒体のテキストを使用して韓国語の勉強をすなどして、ブルーライトを回避するよう努めています。

5. 軽いストレッチやヨガを行う
寝る前に軽いストレッチやヨガを行うと、筋肉の緊張をほぐし、心を落ち着かせる効果があります。リラックスした状態で布団に入れるため、スムーズな入眠が期待できます。筆者のおすすめは、深い呼吸を伴うヨガのポーズ。座り仕事が多いため、太ももや骨盤の前側を伸ばすポーズや、股関節を開くポーズを日課にしています。
6. カフェインやアルコールの摂取を控える
カフェインは覚醒作用があり、摂取後も数時間その効果が持続します。また、アルコールは一時的に眠気を誘発するものの、睡眠の質を低下させます。午後以降はカフェインを含む飲み物(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)の摂取をできれば控えましょう。
とはいえ、夜の会食などでお酒やカフェイン飲料を完全に避けるのは難しいこともあります。そのため、無理せず「減らす」ことを意識してみてください。
とはいえ、夜の会食などでお酒やカフェイン飲料を完全に避けるのは難しいこともあります。そのため、無理せず「減らす」ことを意識してみてください。

7. 快適な寝室環境を整える
寝室の温度は16〜20度、湿度は50〜60%程度が理想とされています。快適な睡眠環境を整えるために、寝る前にお部屋の温度・湿度をきっちり確認する、ということも習慣化してみましょう。
「香り」を活用するのもいいですね。
アロマの香りはリラックス効果を生み、睡眠の質を向上させます。寝室でアロマディフューザーを使用したり、枕に数滴垂らすことで、心地よい香りに包まれながら眠りにつくことができます。ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなどの香りは入眠を促進し、リラックス効果が高いとされています。同じ香りでも日によって感じ方が違うので、楽しみながら深掘りしてみるのも良いでしょう。
以上、質の良い睡眠を得るための、ナイトタイムルーティンとして、有用な手段をまとめてみました。日々のストレスから解放され、リフレッシュした状態で新しい日を迎えるため、夜の長いこの季節にぜひ、見直してみてはいかがでしょうか。
「香り」を活用するのもいいですね。
アロマの香りはリラックス効果を生み、睡眠の質を向上させます。寝室でアロマディフューザーを使用したり、枕に数滴垂らすことで、心地よい香りに包まれながら眠りにつくことができます。ラベンダーやカモミール、サンダルウッドなどの香りは入眠を促進し、リラックス効果が高いとされています。同じ香りでも日によって感じ方が違うので、楽しみながら深掘りしてみるのも良いでしょう。
以上、質の良い睡眠を得るための、ナイトタイムルーティンとして、有用な手段をまとめてみました。日々のストレスから解放され、リフレッシュした状態で新しい日を迎えるため、夜の長いこの季節にぜひ、見直してみてはいかがでしょうか。