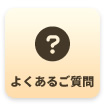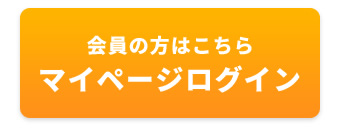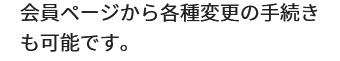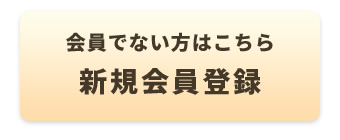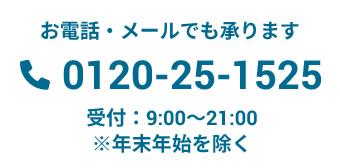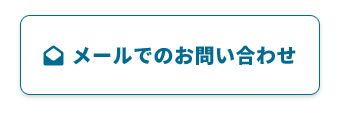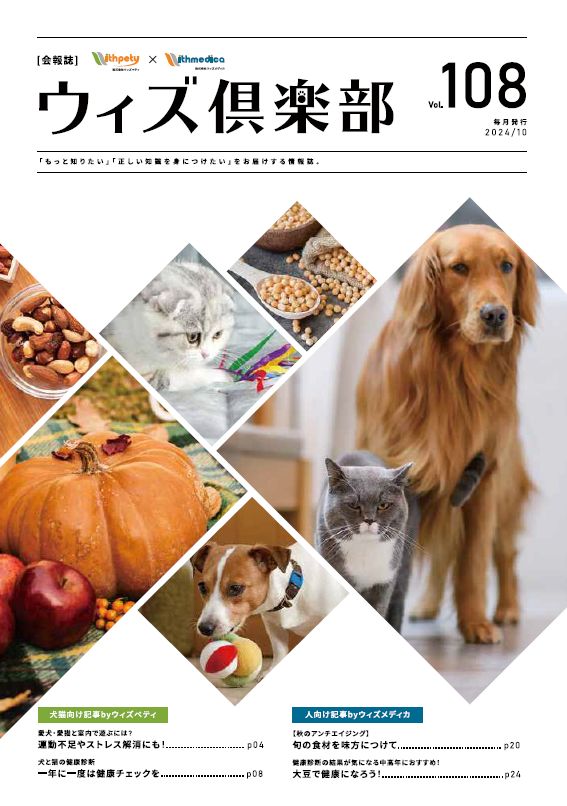【秋のアンチエイジング】旬の食材を味方につけて
執筆者: 橘田 絵里香(形成外科医)
[記事公開日] 2024-08-27 [最終更新日] 2024-09-03
秋は豊富な栄養素を含む食材が多く出回る季節で、アンチエイジング目線でも絶好の機会です。肌を若々しく保つのみならず、全身の健康も基本は食事から!今月は秋のアンチエイジングにおすすめの食材とその効果について詳しく解説します。
[ 目次 ]

さつまいも
さつまいもは食物繊維が豊富であるのみならず、むくみを予防するカリウムが豊富で、先出のカロテノイドのお仲間、βカロテンも見逃せない成分です。皮にはこれまた抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれています。炭水化物率が高めではあるので、接種しすぎに気をつけながら、美味しくいただくことで、腸内環境を整え、便秘の予防に役立つことにより、老化の予防につながります。
おすすめの食べ方:
蒸したり焼いたりしてそのまま食べるも良し、スープやサラダ、デザートにも利用できるさつまいも、ポイントは皮を残すこと!ぜひ皮ごと食べてくださいね。
おすすめの食べ方:
蒸したり焼いたりしてそのまま食べるも良し、スープやサラダ、デザートにも利用できるさつまいも、ポイントは皮を残すこと!ぜひ皮ごと食べてくださいね。

きのこ類
きのこは食物繊維、βグルカンが豊富に含まれており、過食による肥満の予防効果抜群の食材です。βグルカンは先出のカロテノイドやポリフェノールとともに「ファイトケミカル」と呼ばれ、老化の予防や健康の維持に大変役に立つ成分です。各種ビタミンやミネラルも豊富で、免疫力の向上や骨の健康維持に効果があります。
おすすめの食べ方:
きのこは炒め物、煮物、スープ、パスタ、リゾット、お鍋…多彩な料理に使えますよね。秋の味覚としては、きのこを使った炊き込みご飯もいいですが、お鍋にたっぷり放り込むのも時短レシピとして最高です。
おすすめの食べ方:
きのこは炒め物、煮物、スープ、パスタ、リゾット、お鍋…多彩な料理に使えますよね。秋の味覚としては、きのこを使った炊き込みご飯もいいですが、お鍋にたっぷり放り込むのも時短レシピとして最高です。

カボチャ
緑黄色野菜のカボチャはカラダの老化・ストレス物質を除去する効果=抗酸化作用のあるビタミンAの仲間=カロテノイドが豊富に含まれています。強力な抗酸化作用があり、細胞の老化を防ぐことで、視力の保護や免疫力の向上といった効果も見込めます。
おすすめの食べ方:
スープ、サラダ、煮物、スイーツなど、さまざまな料理に使えるのがカボチャの良いところ。暖かいスープやグラタンといった形で取り込むと、体を温める効果もあり、冷え性対策にもなりますよ!
おすすめの食べ方:
スープ、サラダ、煮物、スイーツなど、さまざまな料理に使えるのがカボチャの良いところ。暖かいスープやグラタンといった形で取り込むと、体を温める効果もあり、冷え性対策にもなりますよ!
柿
柿には先出のカリウム、β-カロテン、食物繊維といった成分の他、ポリフェノールの一種であるタンニン、そしてビタミンCが豊富です。ビタミンCは強力な抗酸化作用を持ち、肌の老化を防ぎますが、干し柿にすると失われてしまうので注意が必要です。
おすすめの食べ方:
生柿と干し柿では食感のみならず、その成分にも違いがあります。保存性も高まり、長期間楽しむことができる干し柿は、生柿の栄養成分が凝縮されており、生柿よりも効率よく栄養をとれる一方で、ビタミンCは損なわれてしまいますのでそちらは注意が必要です。そのまま食べるのがのみならず、サラダやヨーグルトに入れても楽しめますよ!
おすすめの食べ方:
生柿と干し柿では食感のみならず、その成分にも違いがあります。保存性も高まり、長期間楽しむことができる干し柿は、生柿の栄養成分が凝縮されており、生柿よりも効率よく栄養をとれる一方で、ビタミンCは損なわれてしまいますのでそちらは注意が必要です。そのまま食べるのがのみならず、サラダやヨーグルトに入れても楽しめますよ!
りんご
果物のなかで、栄養源としてはトップクラスのりんご。海外では「1日1つ食べると医者を遠ざける」などという言い伝えがあるくらいです。抗酸化力のあるポリフェノール、そして食物繊維が豊富にはビタミンC、食物繊維、ポリフェノールが含まれているほか、ビタミンCと、あと注目すべきはリンゴ酸。高血圧の予防や、疲労回復に一役買ってくれますよ…!
おすすめの食べ方:
りんごはそのまま食べるのみならず、サラダ、スムージー、焼きりんごなど、多彩な料理に利用できます。焼きりんごなんて、温かくて甘いデザートとして秋にぴったりです。スイーツとして摂られる場合は糖分の取りすぎにご注意くださいね。
おすすめの食べ方:
りんごはそのまま食べるのみならず、サラダ、スムージー、焼きりんごなど、多彩な料理に利用できます。焼きりんごなんて、温かくて甘いデザートとして秋にぴったりです。スイーツとして摂られる場合は糖分の取りすぎにご注意くださいね。

ナッツ類
8月~10月に収穫され、寒い冬に備えて、古くから食べられてきたナッツ類には、ビタミンやミネラル、食物繊維と、アンチエイジングに有効なさまざまな栄養素が含まれていますが、 特におすすめはアーモンドとクルミ、でしょうかね。
アーモンドにはたんぱく質と食物繊維、抗酸化作用をもつビタミンEが豊富に含まれています。たんぱく質は炭水化物・脂質と並びヒトの体のエネルギー源になる栄養素で、筋肉・臓器・皮膚・毛髪などの体の組織、ホルモン・酵素・抗体などの体内ではたらく成分を構成して、生命の維持に欠かせない物質です。
クルミは他のナッツ類と比較しても、体に良い油分=多価不飽和脂肪酸をたっぷりと含んでいるのが特徴です。多価不飽和脂肪酸は体内で合成できず、食事から摂取しなくてはならない成分で、脂は脂でも、血圧を下げたり悪玉コレステロールを減らしたりする作用を持ち、高血圧や悪玉コレステロールの増加によって引き起こされる生活習慣病に対抗してくれる成分で、予防効果も期待できます。
おすすめの食べ方:
ナッツはそのままスナックとして食べるのが簡単でおすすめです。袋菓子のスナックを食べたくなった時、ナッツに置き換えて食べるのがいいと思います。
アーモンドにはたんぱく質と食物繊維、抗酸化作用をもつビタミンEが豊富に含まれています。たんぱく質は炭水化物・脂質と並びヒトの体のエネルギー源になる栄養素で、筋肉・臓器・皮膚・毛髪などの体の組織、ホルモン・酵素・抗体などの体内ではたらく成分を構成して、生命の維持に欠かせない物質です。
クルミは他のナッツ類と比較しても、体に良い油分=多価不飽和脂肪酸をたっぷりと含んでいるのが特徴です。多価不飽和脂肪酸は体内で合成できず、食事から摂取しなくてはならない成分で、脂は脂でも、血圧を下げたり悪玉コレステロールを減らしたりする作用を持ち、高血圧や悪玉コレステロールの増加によって引き起こされる生活習慣病に対抗してくれる成分で、予防効果も期待できます。
おすすめの食べ方:
ナッツはそのままスナックとして食べるのが簡単でおすすめです。袋菓子のスナックを食べたくなった時、ナッツに置き換えて食べるのがいいと思います。

緑茶
新茶のシーズンではないのですが、温かい飲み物としてリラックス効果もあり、秋冬におすすめな飲み物です。緑茶の主要成分はなんといってもカテキンとビタミンC。抗酸化作用が強く、細胞の老化を遅らせる効果があるのみならず、代謝を高める効果があり、ダイエットにも役立ちます。免疫力を向上させる効果もあり、日本人には外せない飲み物ですよね!
おすすめの飲み方:
なんといってもそのまま飲む、が最強ですが、緑茶が含まれるスイーツを選び、ちょっとだけ罪を軽くするのもいいかも…!?
おすすめの飲み方:
なんといってもそのまま飲む、が最強ですが、緑茶が含まれるスイーツを選び、ちょっとだけ罪を軽くするのもいいかも…!?
まとめ
秋は抗酸化物質や食物繊維が豊富な「旬の食材」を、積極的に取り入れることで、アンチエイジング効果が期待できます。ぜひこの機会に、食生活を見直してみてください!